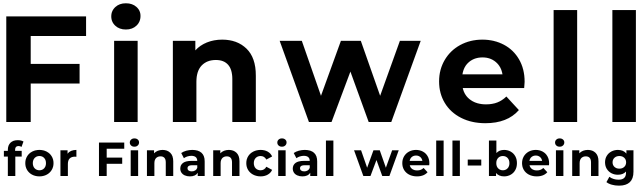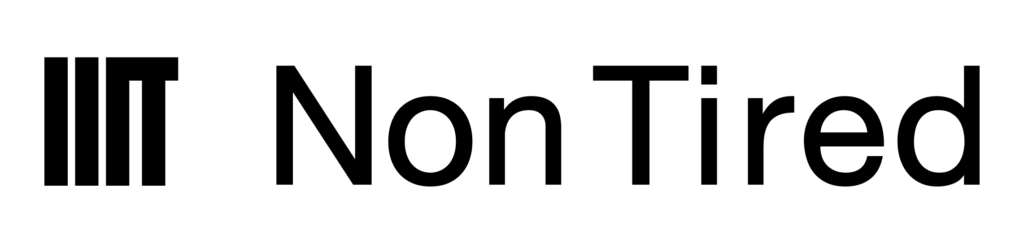「ウェルビーイングってよく聞くけど、実際はどういう意味?」「企業で導入が進んでいるけれど、具体的に何をすればいいの?」このようなお悩みはありませんか。ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に満たされた良好な状態を指し、個人の幸福度を高めるだけでなく、働き方の改善や企業の生産性向上にもつながる重要な概念です。近年では、企業や行政でも積極的に取り入れられています。本記事では、ウェルビーイングの基本的な考え方や構成要素、ビジネスや社会における活用方法を詳しく解説します。具体的な実践方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
ウェルビーイングとは?定義と基本概念を解説
ウェルビーイング(Well-being)は、「心身ともに満たされた状態」を表す言葉です。
単に「健康であること」や「幸せを感じる」だけでなく、「身体的・精神的・社会的な側面がバランスよく整っていること」を意味します。
世界保健機関(WHO)も健康の定義にこのウェルビーイングを取り入れており、近年、重要性が認識されるようになりました。
現代社会では、働き方や生活環境の変化に伴い、身体的・精神的・社会的な側面がバランスが取りづらくなっており、個人や企業にとっても、ウェルビーイングの向上が欠かせない要素となっています。
ここからは、ウェルビーイングについて詳しく解説していきます。
ウェルビーイングの基本的な意味
ウェルビーイング(Well-being)とは、「心身が健やかで、社会的にも満たされている状態」を指す概念です。
単に病気がないことや経済的な安定にとどまらず、人生の充実感や幸福感など、幅広い要素が関係しています。
更には個人の幸福にとどまらず、企業の成長や社会全体の持続的な発展にも影響を与えるとし、注目を集めています。
ウェルビーイングは、個人の主観的な幸福感と客観的な生活環境の両面から成り立つものです。
たとえば、良好な人間関係の構築、やりがいのある仕事への従事、健康的なライフスタイルの維持などが、その実現に大きく関わってきます。
近年では、ビジネスや教育、行政といった多様な分野での導入が進み、持続可能な社会の実現に向けた重要な考え方として広がりを見せています。
主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイング
ウェルビーイングには、「主観的ウェルビーイング」と「客観的ウェルビーイング」という2つの側面があり、これらは、個人の幸福度や生活の質を評価する際に欠かせない指標とされています。
「主観的ウェルビーイング」とは、個人が感じる幸福感や満足度のことです。
たとえば、「日々の生活に対する充実感やポジティブな感情の多さ」「ストレスの少なさ」などが含まれます。
これは、個々の価値観や経験に左右されるため、同じ環境でも人によって感じ方が異なるのが特徴です。
心理学の分野では、人生の満足度や日常の感情のバランスが重要視されています。
「客観的ウェルビーイング」は、健康状態や所得、教育水準、社会的なサポートの有無といった外的な要因によって測定されます。
政府や企業がウェルビーイングの向上を目指す際には、客観的なデータを基に政策や施策を策定することが一般的です。
この2つの側面は切り離して考えるものではなく、密接に関係し、総合的な幸福度を形成します。
そのため、個人の幸福度を高めるには、心の充実だけでなく、健康面や経済的な安定など、生活の基盤を整えることも重要です。
ウェルビーイングの語源と歴史
ウェルビーイング(Well-being)は、英語の「well(良い)」と「being(状態)」を組み合わせた言葉で、「心身ともに充実した良好な状態」を意味します。
この概念は古くから哲学や倫理学の分野で論じられ、幸福や生きがいについて考えるうえで重要とされてきました。
現代においてウェルビーイングが広く認識されるようになったのは、1946年に世界保健機関(WHO)が「健康とは、単に病気がないことではなく、身体的、精神的、社会的に良好な状態である」と定義したことが大きなきっかけです。出典:世界保健機関(WHO)憲章|公益社団法人日本WHO協会
この考え方が浸透したことで、健康を超えた広い視点での「幸福」が重視されるようになりました。
その後、心理学や社会学、経済学などの分野でも研究が進み、個人の幸福度や生活の質を評価する指標として活用されるようになっています。
現在では、個人の生きがいや働き方、地域社会の発展など、多様な場面でウェルビーイングの概念が取り入れられ、より良い社会の実現に向けた取り組みが進められています。
ウェルビーイングを構成する重要な要素とは
ウェルビーイングの実現には、さまざまな要素が関係しています。
世界的な研究機関や専門家たちが、それぞれの視点からウェルビーイングを構成する要素を定義しています。
ここでは、特に重要な2つの理論について詳しく解説していきます。
ギャラップ社が定義する「5つの要素」
ウェルビーイングをより深く理解するために、アメリカの調査会社ギャラップ社は「5つの要素」を定義しています。
これらの要素は、個人の幸福度を高めるだけでなく、社会全体の発展にも貢献する重要な指標とされています。
| キャリア(仕事)ウェルビーイング | 仕事や日常の活動にやりがいを感じ、充実した時間を過ごせていること。 |
| ソーシャル(社会的)ウェルビーイング | 家族や友人、職場の同僚などとの人間関係が良好であること。 |
| ファイナンシャル(経済的)ウェルビーイング | 経済的な安定があり、将来の生活に不安を感じることが少ない状態。 |
| フィジカル(身体的)ウェルビーイング | 健康的な生活習慣を維持し、日々活力を持って過ごせること。 |
| コミュニティ(地域・環境)ウェルビーイング | 自分が住む地域や社会とのつながりを持ち、安心して暮らせる環境が整っていること。 |
これらの5つの要素がバランスよく整っていることが、総合的なウェルビーイングの向上に不可欠です。
企業や自治体でも、この指標を基にした政策や施策を取り入れ、働き方改革や健康経営を推進する動きが進んでいます。
ファイナンシャルウェルビーイングについて詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

PERMA理論に基づく「5つの要素」
PERMA理論は、ポジティブ心理学の権威、マーティン・セリグマン博士による理論です。
5つの要素の頭文字を組み合わせて名付けられました。
| P(Positive Emotion) | 喜びや感謝、満足感などのポジティブな感情を持つこと。 |
| E(Engagement) | 仕事や趣味、スポーツなどに深く没頭する時間があること。 |
| R(Relationships) | 他者との強い結びつきを持つこと。 |
| M(Meaning) | 自分の存在意義を感じること。 |
| A(Achievement) | 目標を持ち、それを達成すること。 |
PERMA理論は、個人だけでなく企業や教育現場でも応用され、働き方改革やメンタルヘルス対策の指標としても活用されています。
この5つの要素を意識することで、より高いウェルビーイングの実現が可能となります。
なぜ今ウェルビーイングが注目されているのか
近年、「ウェルビーイング」という概念が再び注目されるようになっています。
その背景には、価値観の多様化や働き方改革の推進、さらにはSDGsの普及、型コロナウイルス感染症の拡大により生活様式が変化したなど、さまざまな要因が関係しています。
それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。
価値観の多様化
現代社会では、人々の価値観が多様化しており、従来の「経済的な成功」や「社会的な権力」だけを重視するのではなく、「心の豊かさ」や「生活の質」を大切にする傾向が強まってきています。
特に若い世代を中心に、以下のような価値観の変化が見られます。
- 仕事と生活のバランスを重視する
- 精神的な充実感を大切にする
- 個人の幸福感を追求する
- 多様な生き方を認め合う
この背景には、ライフスタイルの変化やテクノロジーの進化が影響しています。
リモートワークや副業の普及により、仕事とプライベートのバランスを重視する人が増えました。
また、SNSを通じて多様な価値観が可視化され、自分に合った生き方を模索する傾向が強まっています。
企業も、従業員のウェルビーイング向上に取り組むことで、満足度を高め、生産性を向上させる動きが進んでいます。
働き方改革の推進
日本では近年、「働き方改革」の推進とともに、ウェルビーイングの重要性がますます高まっています。働き方改革は、長時間労働の是正や多様な働き方の促進を目的とした取り組みであり、企業の生産性向上と従業員の生活の質を向上させることを目的としています。
これまでの日本では、企業戦士という言葉に象徴されるような長時間労働や終身雇用が当たり前のため年功序列制度が一般的でした。しかし、これらの慣習は従業員のストレス増加や健康リスクの上昇につながり、ウェルビーイングを損なう要因として指摘されてきました。
そのため、近年では柔軟な働き方を取り入れる企業が増え、業務効率化による長時間労働の是正、年功序列制度の廃止、テレワークの導入や副業の解禁、フレックスタイム制の活用等の働き方改革が進んでいます。
ウェルビーイングを重視することは、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高め、ひいては企業の成長を後押しする結果につながります。
こうした働き方改革は、企業が持続的に発展していくために欠かせない要素といえるでしょう。
SDGsの普及
ウェルビーイングは、国連のSDGs(持続可能な開発目標)において重要な要素として位置づけられています。
SDGsの中でも、「すべての人に健康と福祉を」をはじめ、以下のような目標がウェルビーイングの考え方と密接に結びついています。
- 健康的な生活の確保と福祉の促進
- 質の高い教育の実現
- ジェンダー平等の推進
- 働きがいのある仕事の提供
こうした目標の達成に向け、企業や行政はウェルビーイングを重視した取り組みを進めています。
人々の幸福と持続可能性は密接に関連しており、ウェルビーイングの向上は社会全体の発展に不可欠な要素とされています。
新型コロナウイルス感染症の拡大により生活様式が変化した
新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしました。
身体的・精神的な健康の重要性があらためて認識され、ウェルビーイングへの関心が一層高まっています。
パンデミックによるテレワークの普及や外出制限の影響で、多くの人が孤独感やストレスを抱えるようになりました。
特に、人との直接的な交流が減少し人間関係が希薄化したことで、社会的なつながりの大切さが浮き彫りになったといえます。
テレワークやオンライン飲み会などの普及で仕事とプライベートの境界が曖昧になり、「ワークライフバランスをどう維持していくか」が課題として浮かび上がっています。
こうした状況を受け、企業や行政は従業員や市民のウェルビーイングを支える施策を積極的に推進しています。
上述した働き方改革の導入サポートや、メンタルヘルスサポートの充実など、持続的な健康と幸福を実現するための取り組みが広がっています。
今後も、こうした流れは加速していくでしょう。
ウェルビーイングを取り入れることで得られるメリット
ウェルビーイングを取り入れることで、さまざまなメリットが得られることが研究により明らかになっています。
従業員の幸福度を高めることは、組織全体の成果にもプラスの影響を与えます。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 生産性の向上と顧客満足度の改善
- 人材確保と定着率アップにつながる
- 良好な人間関係を築き、職場のエンゲージメントを強化
順に解説していきます。
生産性の向上と顧客満足度の改善
ウェルビーイングを取り入れることで、企業の生産性向上が期待されます。
従業員が健康で充実した状態で働ける環境が整えば、業務の効率が上がり、サービスの品質も向上するためです。
ウェルビーイングを重視する企業では、ストレスを軽減し、モチベーションを高めるための施策を積極的に導入しています。
例えば休暇の取得を推奨したり、ワークライフバランスを考慮した柔軟な働き方を促進することで、従業員は心身の健康を維持しながら業務に取り組めるようになります。
環境が整うことで、集中力が高まり、結果として生産性の向上につながります。
さらに、職場環境の改善によって従業員の満足度が向上すれば、顧客対応の質にも好影響を与えます。
前向きな気持ちで働く従業員は、より丁寧で質の高いサービスを提供できるため、最終的に顧客満足度の向上にもつながります。
人材確保と定着率アップにつながる
ウェルビーイングを取り入れることで、企業は優秀な人材を確保し、従業員の定着率を高められます。
働きやすい環境が整えば、社員のソーシャルウェルビーイングが向上し、働き続けたいと思える職場が実現します。
近年、求職者は給与や福利厚生だけでなく、ワークライフバランスや職場の雰囲気も重視する傾向が強まっています。
特に若い世代では、「柔軟な働き方ができるか」「メンタルヘルスへの配慮があるか」といった点を企業選びの重要な基準とする人が増えています。
そのため、ウェルビーイングを推進する企業は求職者にとって魅力的な職場となり、採用競争でも優位に立ちやすくなるでしょう。
さらに、ウェルビーイングの向上によって仕事への満足度が高まると、モチベーションが維持されやすくなります。
その結果、離職率の低下につながり、従業員の定着率が向上するでしょう。
良好な人間関係を築き、職場のエンゲージメントを強化
ウェルビーイングを重視する職場では、従業員同士の良好な人間関係が築きやすく、組織全体のエンゲージメント(組織への愛着や貢献意欲)が高まる傾向があります。
ウェルビーイングの取り組みは、以下のような効果を生み出します。
- オープンなコミュニケーションの促進
- チームワークの向上 ・相互理解と信頼関係の構築
- 組織への帰属意識の強化
- 仕事への意欲と責任感の向上
これらの取り組みによって、職場の雰囲気が良くなるだけでなく、業務の効率が上がり、新たなアイデアが生まれやすくなります。
従業員同士が理解し合い、協力しやすい環境を整えることで、組織全体の活力が向上し、持続的な成長へとつながっていくでしょう。
企業がウェルビーイングを実現するための具体的な方法
企業がウェルビーイングを実現するには、具体的な施策を導入し、それを継続的に実践することが不可欠です。
特に、従業員の健康管理を徹底し、働きやすい環境を整えることが重要なポイントとなります。
では、具体的にどのような取り組みが効果的なのか、詳しく見ていきましょう。
従業員の健康管理を強化する(健康診断やストレスチェックの導入)
企業がウェルビーイングを実現するには、従業員の健康管理を強化することが欠かせません。
定期的な健康診断やストレスチェックを実施することで、従業員の健康状態を把握しやすくなり、適切なサポートが提供できます。
健康診断は、生活習慣病の予防や身体の不調を早期に発見するために重要です。
定期的な検査を受けることで、従業員が自身の健康を意識し、必要な対策を講じるきっかけになります。また、ストレスチェックを導入すれば、職場環境が従業員に与える心理的負担を可視化でき、状況に応じた改善策を講じることが可能です。
加えて、フィットネスプログラムやメンタルヘルスサポートを導入することで、従業員の健康維持を促進できます。
たとえば、ジムの利用補助を実施したり、カウンセリングサービスを提供したりすることで、心身の健康を支える環境を整えられます。
こうした取り組みは、従業員の健康意識を高めるだけでなく、企業全体の生産性向上にも貢献します。
長期的に見ても、健康で充実した職場環境の実現は、企業の持続的な成長を支える要素の一つとなるでしょう。
働きやすい環境を整備する(柔軟な働き方や制度の導入)
ウェルビーイングを向上させるためには、柔軟な働き方や制度の導入が欠かせません。
リモートワークやフレックスタイム制度を取り入れることで、従業員のワークライフバランスが整い、仕事の効率も上がります。
たとえば、リモートワークを導入すれば、通勤時間が削減されるだけでなく、自宅で快適に働ける環境を確保しやすくなります。
その結果、従業員のストレスが軽減し、集中力や生産性の向上にもつながるでしょう。
また、フレックスタイム制度を活用すれば、個々のライフスタイルに合わせた柔軟な勤務スケジュールを組むことが可能です。
これにより、家族との時間を大切にしたり、自己成長のための学習機会を確保したりでき、仕事へのモチベーション向上にも寄与します。
さらに、企業が「育児休暇」や「介護休暇」といったサポート制度を充実させれば、ライフステージの変化に対応しながら働き続けることが可能になります。
こうした取り組みを進めることで、従業員が安心して長く働ける環境が整い、企業の魅力も高まるでしょう。
ウェルビーイングを実現し、より良い生活と社会へ
ウェルビーイングは、個人の幸福や充実感を高めるだけでなく、組織や社会全体の持続的な成長にも欠かせない要素です。
本記事では、その基本概念から実践方法までを幅広く紹介してきました。
ウェルビーイングを実現するためには、以下のポイントが重要です。
- 身体的・精神的・社会的な健康をバランスよく維持する
- 個人と組織の価値観を調和させる
- 継続的な取り組みと改善を重ねる
- 周囲との良好な人間関係を築く
- 持続可能な社会への貢献を意識する
ウェルビーイングは、短期間で達成できるものではありません。
しかし、一人ひとりが意識を持ち、企業や社会全体で取り組むことで、より豊かで持続可能な未来が実現できます。
これからの時代、ウェルビーイングを重視した生き方や働き方が、ますます求められるでしょう。
なお、弊社ではウェルビーイングの中でもファイナンシャルウェルビーイングの観点に重きをおいた、従業員の皆さまへの金融教育プログラムを提供しています。
従業員の皆様のエンゲージメント向上が期待できるだけでなく、金融リテラシーの習得に伴うビジネススキルの向上が期待できる研修プログラムも提供しております。
詳しくは以下のページをご参照ください。
ファイナンシャルウェルビーイングについて詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

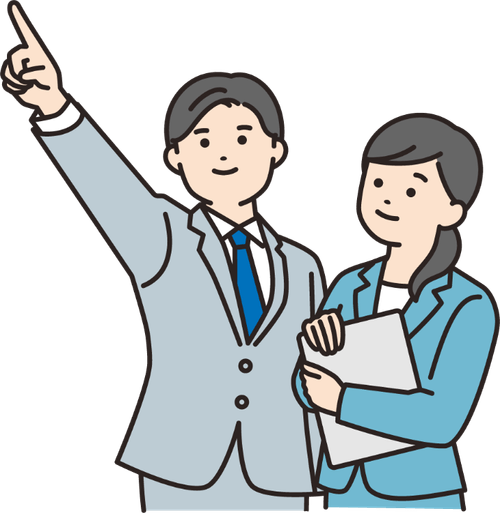
売らないFP コーパス
あなたに寄り添ってお悩みを解決できる
信頼できる独立系FPだけを紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えられるFPとマッチング!
もうFP選びで失敗したくない方へ
売らないFPコーパス
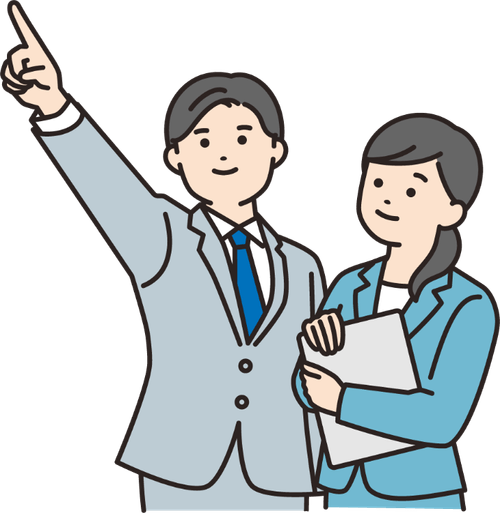
あなたに寄り添って解決できる
信頼できる独立系FPだけを
紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えるFPと
マッチング!
監修者情報:芳川 宏輔

株式会社ウィンカム
CFP認定ファイナンシャルプランナー
金融商品・保険商品を一切販売せずコンサルティングに徹するFP。
保険・住宅ローン・資産運用・NISA等サポートは多岐に渡る。
年間100回以上の面談を実施し、延べ相談実績は300回を超える。
- 当該資料は信頼できる情報、データをもとにNonTired株式会社が作成しておりますが、正確性・完全性に関して当社が保証するものではありません。
- 当該資料に記載された情報、意見は作成時点のものであり、その後の情勢の変化などによって予告なく変更することがあります。
- いずれの情報、データ、意見は将来の傾向などを保証もしくは示唆するものではありません。
- この資料は、投資行動や意思決定を推奨するものではなく、利用者はご自身の責任において活用してください。
- 当該資料に係る一切の権利は引用部分を除いて弊社に所属し、いかなる目的であれ当該資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りします。