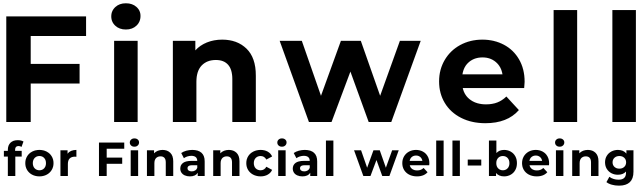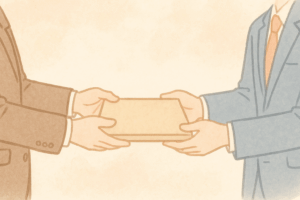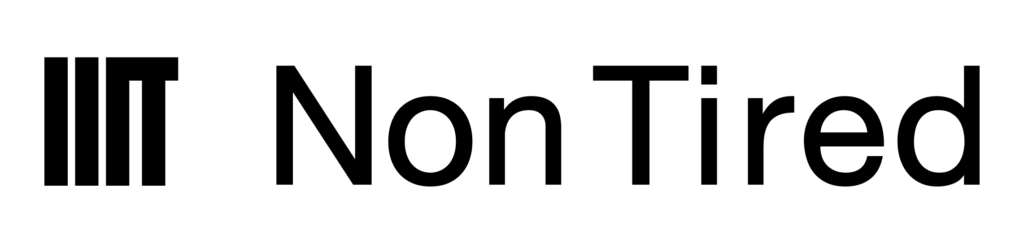将来の教育資金を憂う子育て世代から注目されているのが、「こども支援NISA(仮称)」という新たな非課税投資制度。
23年に終了した「ジュニアNISA」に代わる制度として、26年の導入を目指して検討が進められているものです。
今回は「こども支援NISA」について、お金のプロである独立系FPが解説します。
監修者情報:芳川 宏輔

株式会社ウィンカム
CFP認定ファイナンシャルプランナー
金融商品・保険商品を一切販売せずコンサルティングに徹するFP。
保険・住宅ローン・資産運用・NISA等サポートは多岐に渡る。
年間100回以上の面談を実施し、延べ相談実績は300回を超える。
こども支援NISAとは?

こども支援NISA(仮称)は、未成年の子ども名義で投資信託などを非課税で運用できる制度です。
通常の新NISAは20歳以上が対象ですが、本制度では18歳未満の未成年者を対象とする方向で議論されています。
家庭内での資産形成を後押しし、子どもの教育資金や将来の自立資金の準備に役立ててもらうことを目的としています。
施行はいつから?
「こども支援NISA」は政府の骨太方針(2025年6月)に盛り込まれ、制度設計の議論が進んでいますが、正式な法案化や施行時期は未定です。
しかし、2025年末までに2026年度税制改正大綱へ盛り込むことを目指すと報じられています。
制度施行は早ければ2026年からとなる見通しです。
2025年12月5日最新版!
旧制度「ジュニアNISA」との違いは?
こども支援NISAは、終了した「ジュニアNISA」と多くの共通点がありますが、その改善版とも言える制度です。
| つみたて 投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 投資対象 | 長期分散投資に適した投信 | 上場株や等身など幅広く |
| 年間 投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 総限度額 | 1800万円 | |
| うち1200万円まで | ||
| 対象年齢 | 18歳以上→ 未成年も可能に 上限は別途設定 | 18歳以上 |
ジュニアNISAは制度の考え方はよかったものの、18歳まで原則引き出せないという制限がネックになり、利用者が伸び悩みました。



私も実際に自分の子供のジュニアNISAを開設していますが、現在は、積立も引き出しもできておらず、非常に不便を感じています。
対象年齢を拡大対象年齢を拡大
18歳以上→0歳からに


NISAの口座開設対象を現行の「18歳以上」から「0歳の乳児」まで拡大し、未成年でも利用できるようにする。
親や祖父母が子や孫名義で口座を開設し、運用管理を行う想定です。
引き出し制限を緩和
18歳以上→12歳以上に
最大の特徴が「12歳以降は引き出し可能」とする案です。
従来のジュニアNISAでは原則18歳まで資金を引き出せませんでしたが、この制限を見直し、必要な時期に柔軟に資金を引き出せるようにする方向です。
例えば中学進学(12歳)以降であれば教育費が本格的にかかるため、そのタイミングから必要資金を取り崩せるようにする狙いがあります。


こども支援NISAのメリット
教育資金の計画的な準備に最適
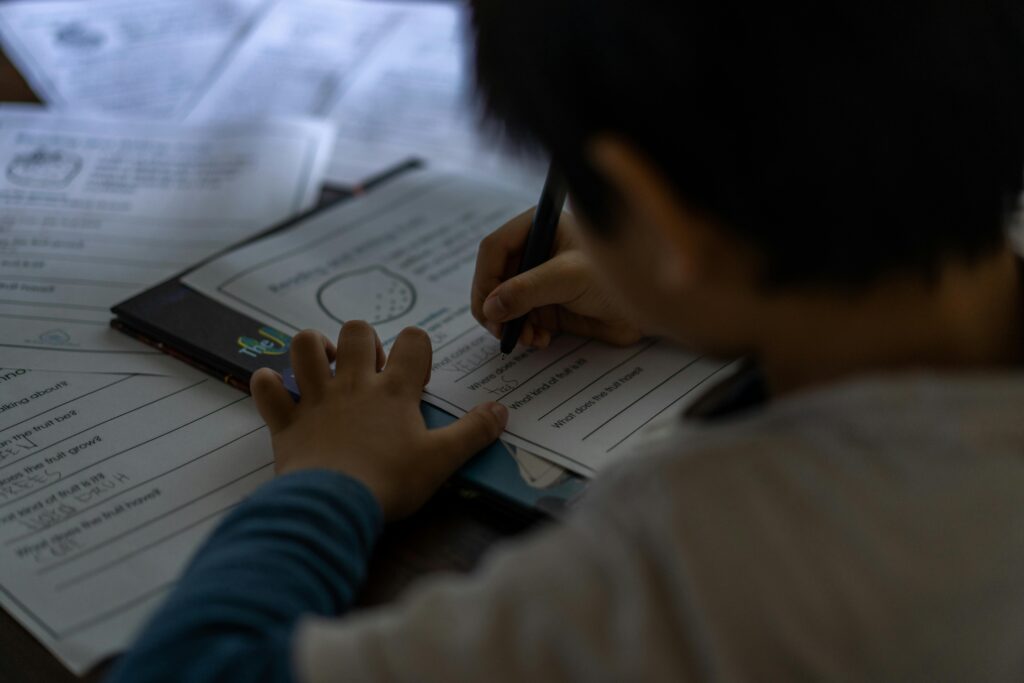
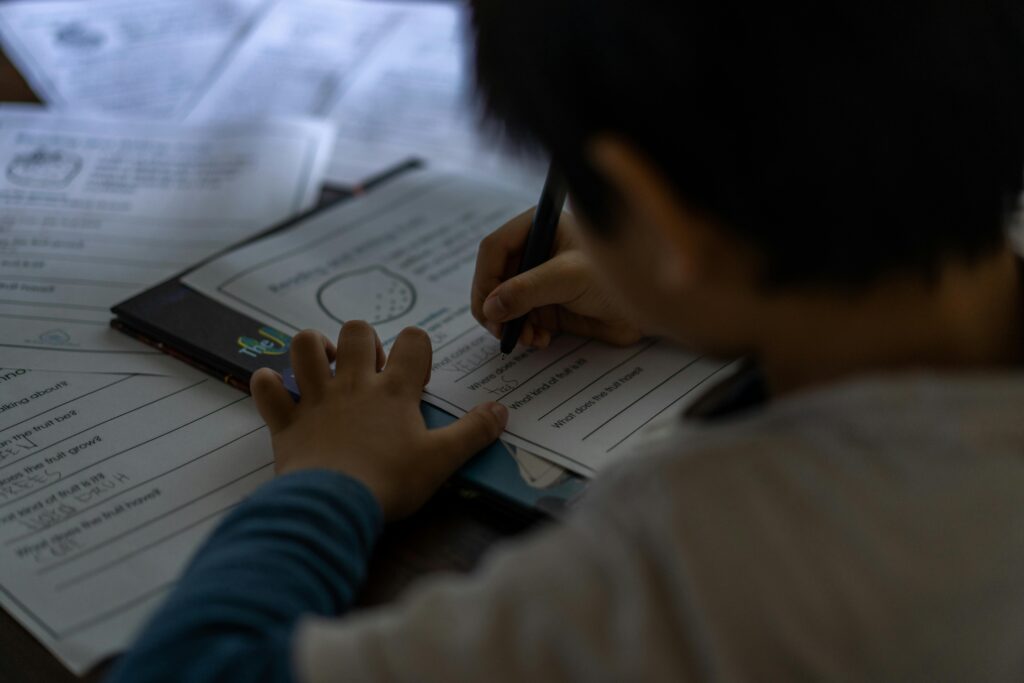
0歳から積立ができれば、出産祝いや児童手当、お年玉等のお金を投資に回すことで、大学進学時などの教育費に備えることができます。
子供に「あの時私/僕が貰ったお年玉使ったでしょ!」なんて事も無くなるかもしれません。
また、NISA枠内で得た運用益は非課税となるため、効率的な資産形成が可能です。
複利効果で資産が増えやすい
たとえば年間10万円を15年間積み立て、年平均4%の運用をした場合、元本150万円に対して運用益が約70万円がつき、合計220万円以上になります。
長期積立+非課税効果=複利の力を活かすことで、将来の負担を軽減できます。
子どもの金融教育にもつながる
「お金を増やす仕組み」や「投資への理解」を親子で学ぶ絶好の機会になります。
成人後の資産形成をスムーズに始める土台作りにもなるでしょう。



私が例えばこの制度を使うのであれば、子供のために頂いたお金は全てこの制度内で運用します。
18歳になった時点で、お金を増やす仕組みや資産運用について金融教育をした上で全てのお金を託して使ってもいいし、引き続き運用をしていくのもいいかなと考えています。(本音はこっちがいいですが)
注意点・デメリットは?
制度詳細が未定である点
まだ制度が検討段階であることから、以下の点には注意が必要です*2025年8月27日現在。
- 制度内容(非課税枠・引き出し条件など)は変更の可能性あり
- 投資商品によっては元本割れのリスクがある
- 名義は子どもになるため、資金の使い道や管理の在り方を明確にする必要がある
- 教育資金の「確実な準備」が必要な家庭では、投資とのバランスが重要
元本割れのリスク
資産運用について一番避けなければいけないのは、元本割れです。
過去20年のデータを分析すると、分散投資をしても5年以内の運用成績では元本割れする割合も多いので、やはり慎重に検討する必要はあります。
独立系FPの観点からは、過去の運用成績からみても、10年以内に使う予定のあるお金、例えば
- 「高校入学金の支払いが2年後にある」
- 「大学入学金が5年以内にある」
- 「3年後に海外留学させたい」
など、直近の支出予定がある場合は、預貯金や定期積立と併用するのが現実的です。
今からできる準備は?
親のNISA口座で教育資金を運用


こども支援NISAの導入を待つ間、何もしないのはもったいないです。
まずは親のNISA口座を使って教育資金を積み立てるのが現実的です。
ご両親自体がNISAをやっていなければ子供への説明や理解も追いつかないため、先に始めていきましょう。
つみたて投資枠を活用すれば、少額からでも長期運用のメリットを享受できます。
余剰資金を確保しておく
こども支援NISAの開始を見越して、お金もしっかり貯めていきましょう。
このタイミングで、家計の見直しや保険の見直しや住宅ローンの見直しを実行し、将来的にどう資金を使うか、何に備えるかを家族で話し合っておくのも良い機会です。
情報をしっかり把握して捉えておく
冒頭申し上げたようにまだどうなるかは全く決定しておりません。
施行されるか、はたまた頓挫するのか、制度が最終的にどうなるのかなど定期的に情報をチェックしていきましょう。
独立系FPはどう使う?



筆者の場合は、仮に制度が開始した際には、直ぐに始めるのではなく、まずは制度について理解することからスタートします。
その上で制度上メリットが大きければ、開設し、ジュニアNISAから移行できる場合には、します。
運用の原資としては、「児童手当+お年玉+お祝い金」を充てて運用をしていきます。
年間の上限額が不明ですが、恐らく贈与税との絡みもあるので、年間110万円を越えない範囲で、拠出することになるでしょう。
また、物心着いたタイミングで、投資教育を家庭でしっかりしたうえで、高校生くらいからは、運用を本人に任せて、アルバイトなどを積立てもよし。
好きに使ってもよし。基本的には本人に任せたいと思います。
監修者情報:芳川 宏輔


株式会社ウィンカム
CFP認定ファイナンシャルプランナー
金融商品・保険商品を一切販売せずコンサルティングに徹するFP。
保険・住宅ローン・資産運用・NISA等サポートは多岐に渡る。
年間100回以上の面談を実施し、延べ相談実績は300回を超える。
まとめ
こどもの未来を“非課税”で支える準備を
こども支援NISAは、教育資金や将来の自立資金を効率的に準備できる、非常に魅力的な制度になる可能性があります。
正式な開始は2026年以降の見込みですが、今からできる準備を始めることで、制度がスタートしたときにスムーズに活用できるようになります。
資産形成は一朝一夕にはいきません。
だからこそ「早く」「少しずつ」「確実に」始めることが、家族の安心につながります。
お子さまの未来のために、こども支援NISAを視野に入れながら、今できる第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
※この記事は2025年8月時点の情報をもとに執筆しています。
制度の詳細は今後変更される可能性がありますので、最新情報は金融庁や関連機関の発表をご確認ください。
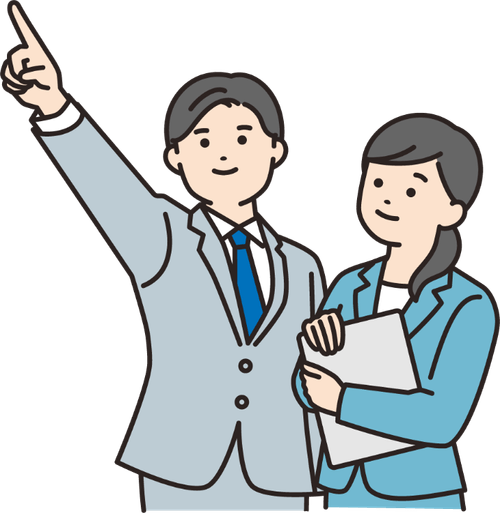
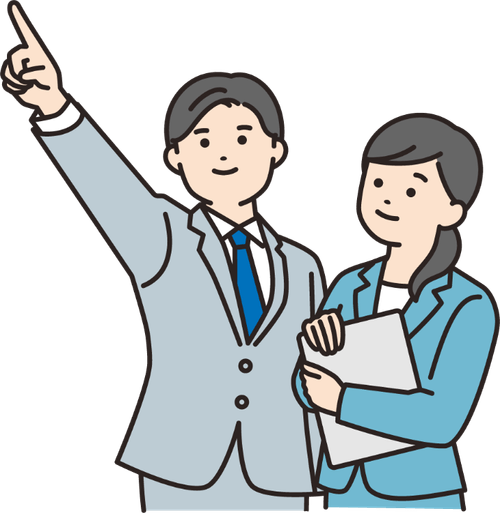
売らないFP コーパス
あなたに寄り添ってお悩みを解決できる
信頼できる独立系FPだけを紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えられるFPとマッチング!
もうFP選びで失敗したくない方へ
売らないFPコーパス
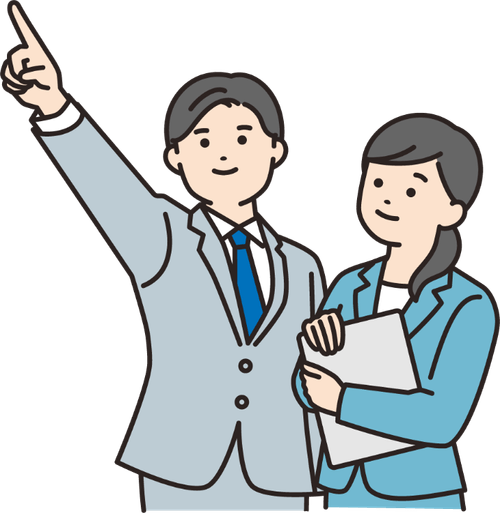
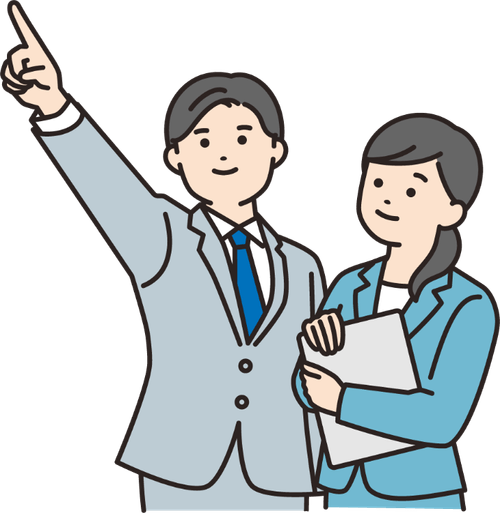
あなたに寄り添って解決できる
信頼できる独立系FPだけを
紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えるFPと
マッチング!
- 当該資料は信頼できる情報、データをもとにNonTired株式会社が作成しておりますが、正確性・完全性に関して当社が保証するものではありません。
- 当該資料に記載された情報、意見は作成時点のものであり、その後の情勢の変化などによって予告なく変更することがあります。
- いずれの情報、データ、意見は将来の傾向などを保証もしくは示唆するものではありません。
- この資料は、投資行動や意思決定を推奨するものではなく、利用者はご自身の責任において活用してください。
- 当該資料に係る一切の権利は引用部分を除いて弊社に所属し、いかなる目的であれ当該資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りします。