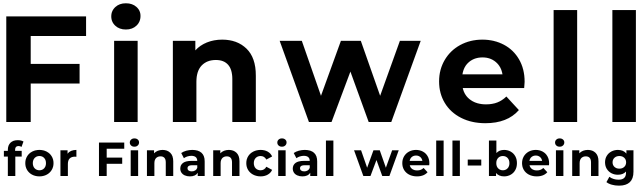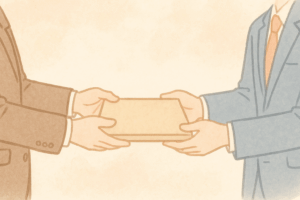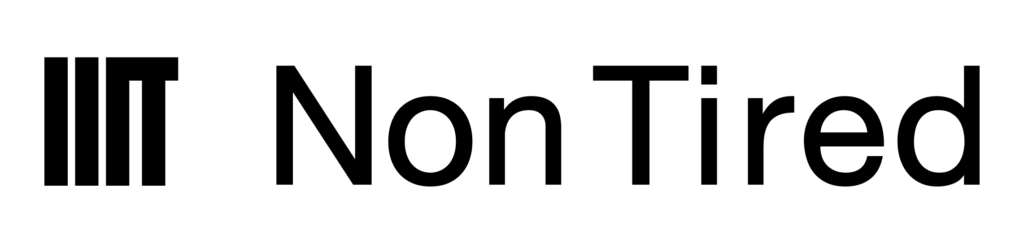子育て世代の住宅ローン、なぜ特別な配慮が必要なのか
住宅購入は人生三大支出の一つですが、教育費や老後の生活まで見据えた長期的な資金計画に配慮する必要があります。独身世帯や夫婦二人世帯とは大きく異なる家計構造を持つ子育て世帯が、安心して住宅ローンを組み、お金に不安のない人生を歩んでいくためには、どのような点に注意すべきでしょうか。
本記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、子育て世帯特有のリスクを踏まえた住宅ローン戦略について詳しく解説します。
子育て世帯特有の家計構造(教育費・生活費の増加、将来の収入変動リスク)
子育て世帯の家計は、独身世帯・夫婦二人世帯と比較して以下のような特徴があります。
教育費・生活費の継続的な増加
- 子どもの成長に伴い教育費が段階的に増加
- 生活費(食費、光熱費、被服費など)も子どもの人数・年齢に比例して増加
- 習い事、塾、部活動など課外活動費の負担増加
また将来の収入変動リスクの高さも考慮する必要があります。例えば育児に伴う残業制限や昇進への影響。配偶者の育児休業による一時的な収入減少。もしくは配偶者の転職・退職リスク等を考え、いつまでどのように働くのか(働けるのか)を考慮しておくことが必要です。
独身・夫婦二人世帯との違い
子育て世帯と独身・夫婦二人世帯の圧倒的な違いは、教育費です。
教育費は一時的な支出ではなく、長期間にわたる大きな支出が発生します。文部科学省・日本政策金融公庫などの調査データによると幼稚園~高校まで(1人あたり)すべて公立の場合で約540万円。すべて私立の場合だと約1,830万円かかります。また大学(4年間)も国公立で約540万円(授業料・生活費含む)私立文系で約740万円、私立理系の場合だと約820~1,000万円かかります。整理すると子ども一人あたりの総額イメージはすべて公立+国公立大学の場合約1,000~1,100万円。私立多め+私立大学理系に行った場合は約2,500万円超になります。
子供がいるいないでこれだけの差がでます。また支出面だけでなく、育児休業や転職などの収入変動のリスクも高く、将来の収支状況を考慮した計画が必要になります。
独身世帯では自分の判断だけで支出をコントロールできますが、子育て世帯では子どもの成長に伴う必要経費は削減が困難です。夫婦二人世帯と比較しても、住居面積の拡大ニーズや立地条件(学校区など)への配慮が必要となり、人気のある立地で、3LDKの間取りの物件では、物件価格が高い傾向があります。
FP視点で見る「ライフイベントの集中による資金圧迫リスク」
子育て世帯では、住宅購入、出産・育児、教育費負担という大きなライフイベントが短期間に集中する特徴があります。筆者自身も現在35歳ですが、30代は子供の誕生や住宅購入などが重なり、資金繰りが大変でした。
FPという仕事柄、事前にライフイベントの時期と金額を予測し、収支のピークとボトムを事前に把握することで焦ることはありませんでしたが、多くの方は事前の想定をしていないケースが多く、この時期は将来への漠然とした不安を抱えるが多いと思います。
物価上昇が住宅ローン計画に与える影響
近年のインフレは生活費や教育費を押し上げ、住宅ローン返済に大きな影響を与えます。本章では、インフレが家計に及ぼす実質的な返済負担の増加や購買力低下リスクを整理し、物価上昇局面における金利タイプの選び方や支出抑制の基本的な対策を解説します。
インフレによる生活費・教育費の上昇が返済余力に及ぼす影響
近年の物価上昇(インフレ)は生活費・教育費に大きな影響を及ぼします。食費・光熱費の継続的な上昇、習い事、塾代の値上がりなど積み重なっていきます。あるモデル世帯のケース:4人家族(夫婦+子ども2人)の場合でどのくらいインフレが影響を与えるかみましょう。月の生活費:約30万円(食費:8万円、光熱費:2万円、日用品・サービス:5万円、家賃・住宅ローン:10万円、その他(交通・教育など):5万円)と仮定します。
2020年から2024年のインフレ率を勘案すると食費(+約10%)光熱費(+約20%)日用品・サービス(+約8%)
家計全体での変化を比較すると2020年月30万円だったものが、インフレを計算すると、2024年は月約31.6万円になります。つまりこれは年間約19万円の負担増になり、家族で1回旅行に行けるくらいの金額にあたります。
実質返済負担の増加と、長期ローンにおける購買力低下リスク
また住宅ローンにも与える影響は大きいです。例えば借入時の年収が600万円の場合で返済額が月10万円の場合(年収に対する返済比率は20%) 10年後の物価上昇(年2%で試算)だと実質年収は約490万円相当の購買力になります。つまり実質返済比率が4.5%上昇し、約24.5%になる計算です。住宅ローン自体はインフレの影響を受けませんが、家計が圧迫されると相対的な負担は増えます。
物価上昇局面で有効な金利タイプ選び・支出抑制策の基本ポイント
ではこのような物価上昇局面で有効な金利タイプはなにかということですが、ここは非常に難しい部分です。
変動金利は金利が比較的低く設定されていますが、今後の金利上昇リスクがあります。変動金利がおすすめの世帯は今後収入増加が見込めて、金利上昇に対応可能な世帯です。また固定金利との差額分をしっかりと運用に回すことができるかも重要です。一方固定金利は借入当初から返済額が確定しており、計画が立てやすいことが大きなメリットです。一方で変動金利と比較して金利が高めになっている点は注意が必要です。固定金利がおすすめの世帯は、収入が安定しており、今後の金利の上昇にあたふたしたくない世帯です。
また物価上昇、住宅ローンの金利上昇を考えると、適切な支出抑制策を実行することも有効です。
固定費削減(保険・通信費)はメスが入れやすい部分です。特に保険の見直しについては、公平中立な立場のFPに相談することが大切です。
教育資金との両立を見据えた返済計画
教育費と住宅ローン返済は時期によって重なりやすく、家計に大きな負担を与えます。ここでは教育費のピークと住宅ローン返済のピークを避ける考え方や、大学進学期を見据えたシミュレーション、教育費積立と両立するための返済期間や金利タイプの工夫を紹介します。
教育資金のピーク時期と住宅ローン返済ピークの重なりを避ける考え方
教育費は一般的に以下の時期にピークを迎えます:
教育費のピーク時期:
- 中学受験期(小学5-6年生):塾代など年50-100万円
- 私立中高一貫校期(中1-高3):年100-150万円
- 大学受験期(高3-大学4年):年150-250万円
住宅ローンの返済ピークは一般的に借入当初の10-15年間です。これらの時期が重なると家計が大幅に圧迫されるため、例えば金利が段階的に変化するタイプのローンに入ることで当初10年は返済額を抑え、教育費負担軽減後に金利が上がっても対応できるようにしておく方法もあります。。また親族からの援助を活用するのもありでしょう。教育資金贈与の特例制度や住宅取得資金贈与の特例を活用することでローンの金額を抑えることができます。
大学進学資金との時期別資金シミュレーション例
Aさん家族の例:5歳と8歳のお子様がおり、大学進学予定は13年後と10年後です。多くの方は特に意識することなく住宅ローンを単純に35年均等返済で組んだ場合、子どもの大学進学時期(10-17年後)には住宅ローン返済が月10万円と学費用が月15-20万円(私立なら年間150-200万円)合わせて月25-30万円になり、プラス生活費がかかると家計が破綻しかねません。
そこで賢い資金計画としては、返済ピークを大学進学前に設定することで最初の10年間は返済額を多めに設定(月12-13万円)し、大学進学時期には返済額を抑える(月7-8万円)方法もあります。この場合では、段階金利(当初期間重点返済)の住宅ローンを検討するのが良いでしょう。もしくは事前にわかっていれば、資金を貯めておくことで対応できるかもしれません。このように、家族のライフイベントを見越した住宅ローン設計が家計管理の成功の鍵になります。
教育費積立との両立に向けた返済期間・金利タイプ選びのポイント
住宅ローンの返済と合わせて教育費の準備を進めていくのは非常に重要です。住宅ローンは「薄く長く」が基本です。例えば返済期間別にみてみると、以下のようになるでしょう。
- 30年返済:月返済額は高めだが、教育費ピーク後の完済が可能
- 35年返済:月返済額を抑えて教育費積立を重視
- 段階返済:当初15年は軽減、その後増額で総利息を抑制
子育て世帯(30代)であれば35年返済が一番多い印象です。薄く長く借りることで、毎月の返済額を抑え、その分を貯蓄に回したり、資産運用に回したりして、教育費も同時に確保していきましょう。また金利タイプの選び方ですが、上記記載のように変動金利、固定金利ともにメリットデメリットがあります。ご自身の考えや価値観にあうタイプを選択しましょう。
共働き前提のローン計画で注意すべきこと
共働き世帯は借入可能額の増加などメリットがある一方、収入減少や育休・転職などのリスクも抱えています。本章では共働きの強みと注意点を整理し、収入の一部減少や片働きになった場合の返済シミュレーションを通じて、安全な返済ライン設定の重要性を解説します。
共働き世帯のメリットとリスク
多くの子育て世帯は産休育休後、職場復帰し、共働き世帯になるケースも多いでしょう。共働きはメリットもありますが、リスクもありますので、理解しておきましょう。メリットとしては例えば住宅ローンを借入する際の、借入可能額の増加(世帯年収ベースでの審査)や住宅ローンをそれぞれの名義で借りた場合(ペアローン)では、住宅ローン控除の夫婦それぞれでの適用可能です。収入面でも片方の収入が減少した場合でも、もう片方の収入で補える点も大きいです。
ただ一方でリスクもあります。育児休業による収入減少やお子様の体調不良による欠勤。転職による収入変動や待機児童問題(保育園に入れない)も考えておく必要があります。
世帯収入の一部減を想定した安全ライン設定
そこで仮に世帯収入の一部が減少or無くなった場合を事前に想定しておきましょう。
住宅ローンの一般的な安全な返済比率目安としては世帯年収に対する返済比率が20-25%以内が一つの目安となります。
具体的な安全ライン設定をみると、夫年収:500万円、妻年収:300万円の場合、世帯年収800万円の20% = 年160万円(月13.3万円)です。仮に奥様が時短勤務やパートになり、世帯年収が650万円になった場合だと、世帯年収650万円の20% = 年130万円(月10.8万円)です。
つまり奥様の収入が一部減少したとしても、月10.8万円以内での返済計画であれば安全な計画となります。
片働きになった場合の返済シミュレーション事例
では、子育てを機に完全に1馬力になった場合はどうなるでしょう。
夫(35歳)年収600万円、妻(33歳)年収350万円で世帯年収950万円で住宅ローン3500万円を借入し、毎月10.2万円(世帯年収の12.9%)のモデルケースで見てみましょう。
仮に妻が専業主婦になった場合:世帯年収は600万円に減少します。この場合の返済比率は20.4%に上昇します。
この場合預貯金や資産運用のバランスで耐えられるのであればそのまま継続してもいいでしょう。
ただ、返済がもし厳しいのであればローンの返済期限を延長してもらい月の返済額を軽減したり、一部繰上げ返済をしたり、他の金利が低いローンに借り換えを検討しましょう。
- 返済期間5年延長:月返済額8.7万円(17.4%)
- 300万円繰上げ返済:月返済額8.9万円(17.8%)
- より低金利での借り換え:月返済額9.8万円(19.6%)
ただどの方法も良し悪しはあります。期限を伸ばすとその分利息分の支払いが増えます。繰り上げ返済すると預貯金が減少し、借り換えも手数料がかかります。どの方法が適切なのかしっかりと判断していきましょう
子育て世帯向け住宅ローン優遇・支援制度
子育て世帯には、金利優遇や補助金など多様な制度が用意されています。ここではフラット35子育て支援型、住宅ローン減税の特例、すまい給付金やZEH補助といった支援策を取り上げ、制度の活用方法や申請時の注意点をまとめます。
フラット35子育て支援型や自治体独自の金利優遇制度
フラット35は18歳未満の子どもがいる世帯または夫婦どちらかが40歳未満の世帯を対象に、フラット35の借入金利を当初5年間年0.25%引き下げる制度です。
対象要件としては、申込時点で18歳未満の子どもがいる。または夫婦どちらかが40歳未満。フラット35の利用条件を満たす。※詳細リンク埋め込み
さらに重要なのは、フラット35Sとの併用です。併用時のメリットとしては、フラット35子育て支援型で0.25%優遇が5年間受けられ、フラット35S(ZEH)で0.5%の優遇が5年間受けられます。つまり0.75%の優遇が当初5年間受けられることになります。この場合3000万円借入の場合、5年間で約110万円の利息軽減効果があります。
フラット35以外でも、自治体独自の補助金もあります。子育て支援が手厚い東京都の場合では、東京ゼロエミ住宅導入促進事業(最大210万円)や太陽光発電設備設置補助(10万円/kW)などがあります。
東京以外にも、各自治体で独自の補助金を用意しているケースもありますので、ご自身のお住まいでどんな制度があるのか確認することをおすすめします。
住宅ローン減税の子育て世帯向け特例
2024年度税制改正により、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する住宅ローン減税が大幅に拡充されました。
拡充内容としては、一般世帯では借入限度額3000万円で控除率が0.7%。控除期間が13年になります。子育て世帯では借入限度額4000万円で控除率0.7%。同じく控除期間は13年です。仮に子育て世帯が借入限度額いっぱいの4000万円まで借りた場合、年間控除額は28万円になり(4000万円×0.7%)になり、13年間の総額は364万円になります。
※実際の控除額は所得税・住民税額に依存するため、事前のシミュレーションが重要です。
補助金・助成金制度(例:すまい給付金、ZEH補助)
次に子育て世帯が活用できる主な補助金制度とその特徴をご紹介します。
こどもエコすまい支援事業(2024年度)では、ZEH住宅の場合100万円。長期優良住宅の場合80万円。認定低炭素住宅の場合は80万円が補助となります。ただし工事着手前の申請が必要であったり、予算枠があり先着順で締め切られてしまうこともありますので、注意が必要です。また住宅会社による代理申請が一般的ですので、要件や手順など確認しましょう。ほかにも地域型住宅グリーン化事業などもあります。細かい要件については別途ご確認ください。
制度活用の注意点と申請手順の概要
子育て世帯は特にお金が同時多発的にかかるタイミングです。使える制度は最大限利用して、活用するべきです。ただし複数の制度を併用する場合は注意しましょう。全てが併用出来るわけではないので、うまく活用して最大額の控除や補助が受けられるようにしましょう。
併用可能な組み合わせとしては、例えば「フラット35子育て支援型 + 住宅ローン減税 + こどもエコすまい支援事業」の組み合わせや「地域型住宅グリーン化事業 + 住宅ローン減税 + 自治体補助」などがあります。
逆に併用不可の組み合わせ例としては、「こどもエコすまい支援事業 + 地域型住宅グリーン化事業」※同一住宅で両方は不可などがあります。住宅メーカーやFPにどの組み合わせが併用可能か確認しましょう。
また申請については建築(または購入)される不動産屋、ハウスメーカー、工務店の担当者と密に連絡を取り、滞りなく進めていくのがいいと思います。
将来のライフプランに沿ったローン見直しのタイミング
住宅ローンは長期にわたるため、金利変動や収入変化に合わせた定期的な見直しが不可欠です。本章では借り換えや繰り上げ返済を検討すべき条件、教育費負担が減少する時期の戦略変更、そしてFP相談を活用するメリットを解説します。
金利変動や収入変化に応じた見直しタイミング(借り換え・繰り上げ返済など)
住宅ローンの借り換えメリットが出る一般的な条件は①ローン残高が1000万円以上残っている。②残返済期間が10年以上ある。現状との金利差が1%以上あること。が目安となります。金利が上昇したからといって慌てて返済をするのではなく、ポイントを抑えましょう。しかし、子育て世帯の場合は、これらの条件を満たさなくても借り換えメリットが出るケースがあります。例えば子育て世帯向け優遇制度が利用できる金融機関への借り換えが出来るのであれば検討しましょう。
また収入が変化したタイミングに応じた返済計画の調整が重要です。毎月の収入がプラスに推移した場合は、繰り上げ返済をすることで期間短縮型で総利息削減したり、ボーナス返済を検討しましょう。ただ住宅ローンが上昇傾向にあるとはいえ、低金利でお金を借りることができるのであれば、資産運用との併用を強く推奨します。
FP相談で解決した事例
実際の共働き子育て世帯の事例を通して、住宅購入や教育費準備の課題、FP相談で見えた根本問題、そして具体的な改善策と成果を紹介します。
ケーススタディ:教育費と住宅ローンの両立に悩む共働き世帯
相談者プロフィール: 田中さんご夫婦(仮名)
- 夫:太郎さん(34歳)会社員、年収580万円
- 妻:花子さん(32歳)パート勤務、年収200万円
- 子ども:長女みさきちゃん(6歳)、長男ゆうきくん(4歳)
- 居住地:埼玉県さいたま市
- 現状:賃貸マンション(家賃月10万円)
相談前の課題
田中さんご夫婦が筆者の事務所を訪れたのは、2023年の春でした。花子さんの第一声は「このままでは家も買えないし、子どもたちに満足な教育も受けさせてあげられない。でもどうしたらいいのかわからない」という切実なものでした。
住宅購入への不安
- 希望物件:3500万円のマンション(駅徒歩8分、3LDK)
- 頭金準備:現在500万円(目標1000万円まで不足)
- 月返済額:約10万円の予想(現在家賃とほぼ同額)
- 不安要素:「教育費や老後も含めて本当に35年間払い続けられるのか」
教育費準備の遅れ
- 習い事費用:現在月3万円→将来月10万円の見込み
- 大学資金:「全く貯められていない」状態
- 教育方針:「子どもには良い教育環境を」という強い希望があります。
家計管理の課題
- 毎月の貯蓄:不定期で月2-5万円程度
- 家計簿:花子さんが管理していますが、なかなかお金が貯まらない
- 固定費:加入依頼保険の見直しや固定費の見直したことがない
- 将来計画:漠然とした不安しかない
初回相談で見えた根本問題
詳しくヒアリングを行った結果、田中さんご夫婦の問題は単純な「お金が足りない」ということではなく、より根本的な課題にあることが分かりました。
問題の本質:
1. 優先順位の混乱 住宅購入、教育費準備、老後資金準備のすべてを同時に、そしてすべてを完璧に行おうとして、結果的にどれも中途半端になっている状態であることが判明しました。
2. 情報不足による機会損失 また日々の忙しさに忙殺され、子育て世帯向けの各種制度や優遇措置について調べる暇もなく情報を全く知らず、本来受けられる税制優遇や補助を逃している可能性が大きいことがわかりました。
3. 収支管理の甘さ また家計簿はつけているものの、基本的に記録しているだけで、固定費の見直しや目標設定ができておらず、なんとなく家計管理をしている状況でした。
4. 夫婦間の認識ずれ 住宅購入や教育方針について、夫婦で十分な話し合いができておらず、方向性が一致していない。
FPが提案した解決策
これらの問題を解決するため、筆者は以下の段階的アプローチを提案しました。
①まずは現在の状況を把握することが最優先です。家計を可視化し、最適化するように実行しました。
- 固定費削減:月3.2万円の削減に成功
- 生命保険見直し:月2.3万円削減
- サブスク整理:月0.4万円削減
- 電気・ガス会社変更:月0.5万円削減
- 家計管理システム構築:
- 目標別積立口座の開設
- 自動積立システムの構築
- 月次振り返りルーティンの確立
- 家計管理システム構築:夫婦間の方針統一
- 住宅購入と教育方針についての夫婦会議実施
- 優先順位の明確化
- 役割分担の決定
②次に目標の確認です。購入計画について無理がないか、実現可能かを検討しました。物件のグレードを落とすことは最終手段と考え、希望の条件を満たす物件を購入するために資金計画の最適化を実行支援。
- 頭金:1,200万円(親からの援助700万円を住宅取得資金贈与を活用)
- 借入額:2300万円(当初計画より700万円削減)
- 月返済額:約7.8万円(家賃より削減)
合わせて利用可能な制度を最大限活用します。
- 住宅ローン減税:13年間で約200万円の控除
- すまい給付金:30万円
- 自治体補助金:50万円
- 親からの贈与特例活用:贈与税負担なし
③合わせて教育資金の準備についても計画的に準備を進めるように提案しました。
今後大きくかかる資金としては大学資金があります。目標金額として子ども一人当たり500万円と仮定し、両親のNISAにて年40万円を5年で二人で運用をしていきます。合わせて児童手当も全額NISA制度を活用していくことで、総額約400万円を見据え、足りない分は子育てが落ち着いたタイミングで妻に正社員復帰も視野検討を進めます。
相談後の改善結果
提案実施から2年経過時点での成果としては、固定費や生活費を無理のない範囲で見直し、月12万円の積立を確保しています。(年間144万円)また無事に物件の購入も済み、ローンの返済をしながらも、教育資金の積立として年間120万円ペースで継続されています。FPに相談し、現状把握、適切な対策をとったことで、夢や目標を実現することができました。
子育て世帯が安心して住宅ローンを組むために
最後に、教育資金とのバランスを意識した計画、共働きリスクを織り込んだ返済設計、各種制度の活用と定期的な見直しという3つのポイントを総括します。これらを実践することで、子育て世帯が安心して住宅ローンを返済し、安定した家計運営を実現できます。
教育資金とのバランスを意識した計画の重要性
子育て世帯の住宅ローン計画で最も重要なのは、教育資金との適切なバランスです。文部科学省の調査によると、幼稚園から高校まで全て私立に通った場合の教育費は約1,800万円、大学まで含めると2,000万円を超えることも珍しくありません。住宅ローンの返済と教育費の支払いが重なる時期を事前に把握することが重要です。特に以下の時期は資金需要が高まります。一般的に住宅ローンの返済比率は年収の25-30%以内とされていますが、子育て世帯の場合は20-25%程度に抑えることを推奨します。これにより、教育費の増加や予期しない出費にも対応できる余裕を確保できます。
共働きリスクを織り込んだ返済計画のメリット
現代の子育て世帯の多くが共働きですが、住宅ローンの返済計画を夫婦両方の収入に全面的に依存することは大きなリスクを伴います。妊娠・出産、育児、介護、転職、病気など、様々な理由で一方の収入が減少する可能性があるためです。理想的な返済計画は、夫婦のうち収入の高い方の収入だけでも返済可能な水準に設定することです。具体的には以下のようなアプローチが有効です。子育て期間中は働き方が変化しやすい時期です。時短勤務、在宅ワーク、転職などにより収入が変動する可能性を考慮し、返済計画には十分な余裕を持たせることが重要です。
『制度活用+定期的な見直し』が家計の安定につながる
子育て世帯が利用できる制度は多数あります。これらを積極的に活用することで、住宅ローンの負担を軽減できます。使える子育て支援制度も積極的に活用しましょう。住宅ローンは長期間にわたる返済のため、定期的な見直しが欠かせません。
また手元にある程度資金を用意しておく必要があります。基本的には生活費の6ヶ月分を目安とした預貯金は確保し、教育資金専用の積立を並行して実施していくことも大切です。資産形成の並行実施については、NISAを活用した長期投資+iDeCoによる老後資金の形成も同時進行していきましょう。
まとめ
子育て世帯が安心して住宅ローンを組むためには、単に現在の収入だけを考えるのではなく、将来にわたる包括的な視点が必要です。教育資金との適切なバランス、共働きリスクを織り込んだ堅実な返済計画、そして各種制度の活用と定期的な見直しという三つの柱を意識することで、長期的に安定した住宅ローン返済が可能になります。
住宅購入は家族の夢を実現する大切な一歩ですが、その後の家計運営こそが真の意味での「安心できる住まい」を実現するカギとなります。専門家と相談しながら、ご家庭に最適な住宅ローン計画を立てていきましょう。
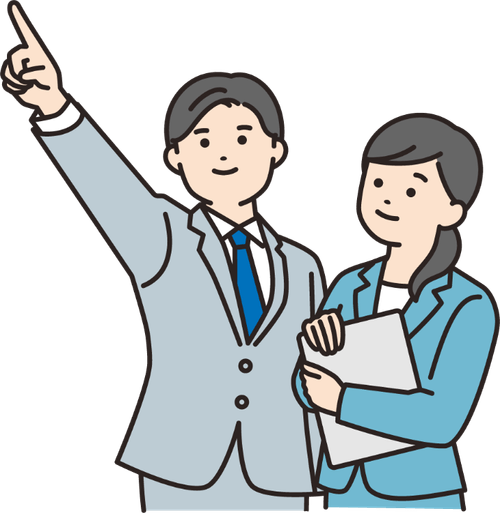
売らないFP コーパス
あなたに寄り添ってお悩みを解決できる
信頼できる独立系FPだけを紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えられるFPとマッチング!
もうFP選びで失敗したくない方へ
売らないFPコーパス
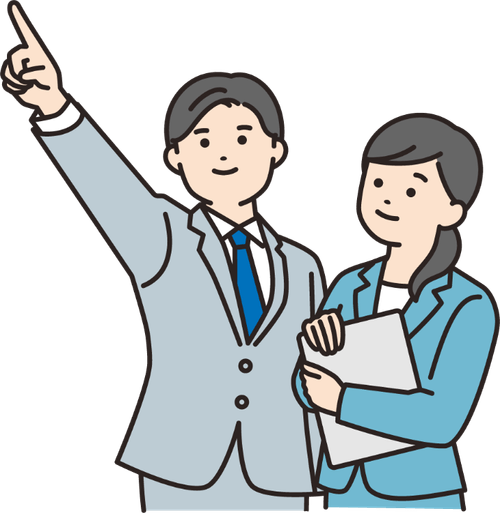
あなたに寄り添って解決できる
信頼できる独立系FPだけを
紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えるFPと
マッチング!
監修者情報:芳川 宏輔

株式会社ウィンカム
CFP認定ファイナンシャルプランナー
金融商品・保険商品を一切販売せずコンサルティングに徹するFP。
保険・住宅ローン・資産運用・NISA等サポートは多岐に渡る。
年間100回以上の面談を実施し、延べ相談実績は300回を超える。
- 当該資料は信頼できる情報、データをもとにNonTired株式会社が作成しておりますが、正確性・完全性に関して当社が保証するものではありません。
- 当該資料に記載された情報、意見は作成時点のものであり、その後の情勢の変化などによって予告なく変更することがあります。
- いずれの情報、データ、意見は将来の傾向などを保証もしくは示唆するものではありません。
- この資料は、投資行動や意思決定を推奨するものではなく、利用者はご自身の責任において活用してください。
- 当該資料に係る一切の権利は引用部分を除いて弊社に所属し、いかなる目的であれ当該資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りします。