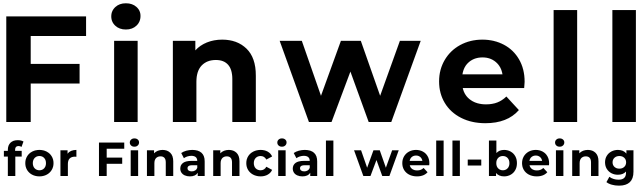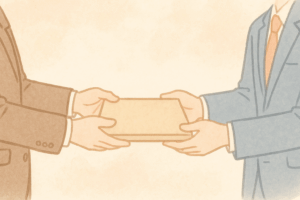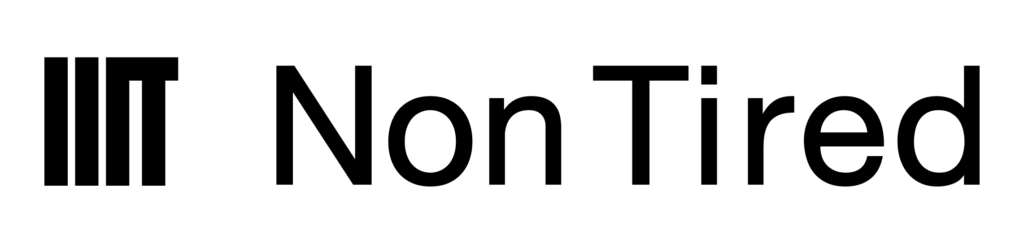「教育資金はいつから準備すればいいのだろう」「教育資金を貯めるなら貯蓄と運用、どちらを選ぶべきなんだろう 」このようなお悩みはありませんか?教育資金の準備は、お子さんの将来を支えるために欠かせない重要なステップです。計画的に貯蓄や運用を進めることで、家計の負担を抑えつつ、安心して教育を受けさせられます。この記事では、教育資金の具体的な貯め方や運用方法、必要な総額、準備を始める適切なタイミング、毎月の積立額の目安などについて詳しく解説します。将来に向けて無理のない資金計画を立てるための参考に、ぜひ最後までご覧ください。
教育資金の準備はいつから始めるべき?必要な金額と計画の立て方
教育資金の準備は、子どもの将来に大きな影響を与える重要な課題です。
事前に計画を立て、必要な金額を把握することで、家計への負担を軽減し、子どもに質の高い教育を提供できます。
以下では、教育資金の準備開始時期と、幼稚園から大学までに必要な総額について詳しく説明します。
教育資金の準備はいつから始めるべき?
教育資金の準備は、子どもが生まれた時点から始めることが理想的です。
たとえば、大学進学時に300万円を用意する場合、0歳から準備を始めると18年間で月々約1.4万円の積立が必要ですが、10歳からでは8年間で月々約3.1万円と負担が増加します。
早期に積立・運用を開始することで、長期間にわたり資産形成ができるので、このように毎月の負担を軽減できます。
教育資金の総額はいくら必要?(幼稚園から大学まで)
子どもの教育費用は、進学先や学校の種類(公立・私立)によって大きく異なります。
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によれば、幼稚園から高校まですべて公立の場合、教育費の総額は約570万円とされています。
一方、すべて私立の場合は約1,830万円が必要です。
さらに、「日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」(2021年度)」よると、大学の費用は、国公立大学では約480万円、私立大学文系で約690万円、私立大学理系では約820万円が必要です。
これらを合計すると、すべて公立の場合で約1,050万円、すべて私立の場合は約2,650万円となり、進路選択によって必要な金額が大きく変動します。
このように、教育資金の準備は早めに始めることが重要です。子どもの将来の希望や家計の状況を踏まえ、無理のない計画を立てることで、安心して教育費を確保できるでしょう。
教育資金準備の3つの基本的な方法とメリット・デメリット
子どもの教育資金を効果的に準備するためには、主に以下3つの方法があります。
- 預貯金での準備方法
- 学資保険での準備方法
- 資産運用での準備方法
それぞれの特徴を理解し、家庭の状況や目標に合わせて選択することが重要です。
預貯金での準備方法
預貯金は、銀行や郵便局の口座に定期的にお金を預けることで教育資金を積立てる方法です。
元本が保証されているうえ、必要なときにすぐ引き出せる柔軟性が大きなメリットといえます。
ただし、現在の低金利環境では利息による増加はほとんど期待できず、物価の上昇により資金の実質的な価値が下がるリスクも考えられます。
また、自由に引き出せる反面、計画的な貯蓄が難しくなることもあるため、使い方には注意が必要です。
学資保険での準備方法
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険商品です。
契約時に定めた年齢に達すると、満期保険金や祝い金を受け取れます。
また、契約者(親)が死亡した場合、以後の保険料の支払いが免除される保障が付いている商品もあります。
一方で、途中解約すると元本割れのリスクがあり、保険料の支払いが家計の負担となる可能性もあるでしょう。
さらに、利回りはあまり高くないため、物価上昇により受け取る金額が実質は下がる可能性があるのも注意が必要です。
資産運用での準備方法
資産運用による教育資金の準備は、株式や投資信託などの金融商品を活用し、資産を増やす方法のひとつです。
長期的な運用を前提とすれば、預貯金や学資保険と比べて高いリターンが期待できます。
一方で適切な資産運用を行うには投資に関する知識や情報収集が欠かせません。
投資には元本割れのリスクが伴い、市場の変動によって資産が減少する可能性もあるため、慎重な運用が求められます。
資産運用の基本は「長期投資」です。短期間で大きな成果を求めるのは難しいことも理解しておきましょう。
なお『売らないFP コーパス』で相談できるFPは金融商品(保険や証券)を販売することを前提としない相談が可能なので、相談者の状況に合わせたライフプランを作成し、最適な教育資金の作り方を提案します。
教育資金の準備に関して「迷っている」「悩んでいる」「このやり方で正しいのか知りたい」とお考えでしたら、お気軽にお申し込みください。
教育資金の準備をする前に家族でやること
子どもの将来の教育を支えるためには、家族全員での話し合いと計画が欠かせません。
以下に、教育資金の準備を始める前に家族で取り組むべき3つのステップを紹介します。
- 教育方針と進学プランを家族で話し合う
- 必要な教育資金の目安を確認する
- 家計の見直しと貯蓄可能額の確認
教育方針と進学プランを家族で話し合う
まずは、子どもの教育について家族で具体的な方針を話し合うことが大切です。
中学受験からするのか高校からなのか、公立か私立か、習い事の選択、大学進学の有無など、教育に関する基本的な方向性を決めていきます。
子どもが小さいうちは、確定的な計画を立てるのが難しいものの、大まかな方針を共有しておくことで、必要な教育資金の見通しを立てやすくなります。
また、教育観や価値観について話し合うことで、将来的な方針の見直しにも柔軟に対応できるでしょう。
この話し合いにより、教育に対する家族の価値観を統一し、将来的な教育費用の目標額を明確にできます。
必要な教育資金の目安を確認する
教育方針が決まったら、それに基づいて必要な教育資金の総額を試算しましょう。
幼稚園から大学までの学費に加え、入学金、制服代、教材費、通学費用なども含めて計算することが大切です。
また、習い事や学習塾などにかかる費用も忘れずに考慮する必要があります。
特に私立学校を選択する場合、公立と比べて大きな費用差が生じる点を認識しておくことが重要です。
想定外の出費にも対応できるよう、複数のケースを想定しながら幅を持たせた試算を行うと安心です。
家計の見直しと貯蓄可能額の確認
最後に、現在の家計状況を見直し、毎月どの程度の金額を教育資金として貯蓄できるかを確認しましょう。
収入と支出を把握し、無駄な出費を減らすことで、貯蓄に回せる金額を増やせます。
たとえば、通信費や保険料の見直し、外食費の削減などが効果的です。
また、児童手当などの公的支援を活用し、それらを教育資金として積み立てるのも一つの方法です。
家計の健全化と計画的な貯蓄を進めることで、子どもの将来の選択肢を広げられます。
もし家計の見直しが難しい場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのもおすすめです。FPは家計管理や教育資金の計画に関する専門知識を持ち、各家庭の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供してくれます。
適切なプランを立てることで、より安心して教育資金を準備できるでしょう。
教育資金を効率的に準備するためのコツ
子どもの将来に備えて、教育資金を効率的に準備することは重要です。
以下に、効果的な3つのポイントをご紹介します。
- 早めに準備を始めることが成功のカギ
- 目的に合わせた貯蓄・運用方法を選ぶ
- 公的支援制度や奨学金も活用する
それぞれについて詳しく解説していきます。
早めに準備を始めることが成功のカギ
教育資金の準備は、早く始めるほど家計への負担を軽減しやすくなります。
たとえば、子どもが0歳のときから毎月1万円を積み立てると、18歳になる頃には約216万円を確保できます。
一方で、開始時期が10歳になると、同じ金額を用意するためには毎月2万円以上の積立が必要になり、家計への負担が大きくなりがちです。
そのため、できるだけ早い段階から計画的に積み立てを始めることで、無理なく教育資金を準備しやすくなります。
余裕を持って資金を確保するためにも、早めの対策を心がけることが大切です。
目的に合わせた貯蓄・運用方法を選ぶ
教育資金は、必要になる時期に応じて適切な貯蓄・運用方法を選ぶことが大切です。
たとえば、幼稚園や小学校の入学金など、近い将来に必要な資金は、安全性の高い預貯金で確保すると安心です。
一方、大学進学時の資金のように時間的な余裕がある場合は、学資保険や投資信託など、より高い運用効率が期待できる方法を検討できます。
また、リスクを分散させるために、一部を定期預金や債券で確保し、残りを投資信託などで運用するのも効果的な方法です。
資金の使用時期を考慮しながら、無理のないバランスで資産形成を進めましょう。
公的支援制度や奨学金も活用する
教育資金の負担を軽減するには、公的支援制度や奨学金の活用も視野に入れるとよいでしょう。
たとえば、児童手当は子どもの成長に応じて支給されるため、計画的に貯蓄すれば教育資金として有効に使えます。
また、大学進学時には、返済不要の給付型奨学金や、低金利で利用できる貸与型奨学金など、多様な支援制度が整っています。
こうした制度を上手に活用することで、家計の負担を抑えながら、子どもの学びの機会を確保しやすくなるでしょう。
支援制度の内容や申請条件を事前に確認し、無理のない資金計画を立てることが大切です。
教育資金準備に活用できる制度とサービス
教育資金を効率的に準備するためには、以下の制度やサービスの活用が有効です。
| 制度 | 特徴 |
| 児童手当 | 2024年10月から制度が拡充され、高校生年代まで支給期間が延長所得制限が撤廃され、第3子以降の月額手当が増額 |
| NISA(少額投資非課税制度) | 新しいNISA制度を活用することで、年間120万円までの投資が非課税となり、長期的な資金運用が可能 |
| 学資保険 | 子どもの進学スケジュールに合わせて受取時期を設定でき、計画的な積立が可能 |
| 銀行の自動積立商品 | 定期的な積立を自動化し、計画的な資金準備が可能 |
| 教育資金贈与信託 | 祖父母などから孫への教育資金贈与に対する税制優遇制度で、1,500万円までの非課税枠がある |
これらの制度やサービスを組み合わせることで、家庭の状況や目標に合わせた効果的な教育資金の準備ができるでしょう。
教育資金の準備をする前にお金の専門家ファイナンシャルプランナーに相談しよう
本記事では、教育資金を効果的に準備する方法について解説しました。
教育資金の計画は、家計全体のバランスを考慮しながら、できるだけ早めに取り組むことが大切です。
しかし、最適なプランを自分だけで立てるのは難しいと感じることもあるでしょう。
そのような場合は、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのがおすすめです。
『売らないFP コーパス』で相談できるFPは金融商品(保険や証券)を販売することを前提としない相談が可能なので、相談者の状況に合わせたライフプランを作成し、最適な教育資金の作り方を提案します。
教育資金の準備に関して「迷っている」「悩んでいる」「このやり方で正しいのか知りたい」とお考えでしたら、お気軽にお申し込みください。
お子様の未来をしっかり支えるために、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
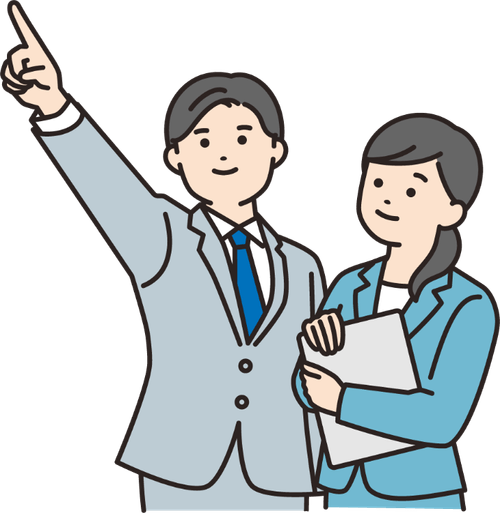
売らないFP コーパス
あなたに寄り添ってお悩みを解決できる
信頼できる独立系FPだけを紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えられるFPとマッチング!
もうFP選びで失敗したくない方へ
売らないFPコーパス
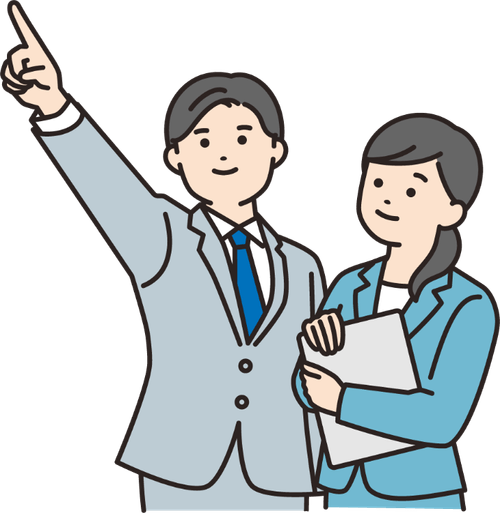
あなたに寄り添って解決できる
信頼できる独立系FPだけを
紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えるFPと
マッチング!
監修者情報:芳川 宏輔

株式会社ウィンカム
CFP認定ファイナンシャルプランナー
金融商品・保険商品を一切販売せずコンサルティングに徹するFP。
保険・住宅ローン・資産運用・NISA等サポートは多岐に渡る。
年間100回以上の面談を実施し、延べ相談実績は300回を超える。
- 当該資料は信頼できる情報、データをもとにNonTired株式会社が作成しておりますが、正確性・完全性に関して当社が保証するものではありません。
- 当該資料に記載された情報、意見は作成時点のものであり、その後の情勢の変化などによって予告なく変更することがあります。
- いずれの情報、データ、意見は将来の傾向などを保証もしくは示唆するものではありません。
- この資料は、投資行動や意思決定を推奨するものではなく、利用者はご自身の責任において活用してください。
- 当該資料に係る一切の権利は引用部分を除いて弊社に所属し、いかなる目的であれ当該資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りします。