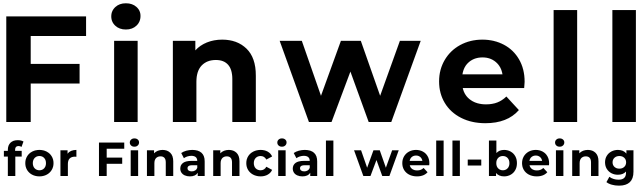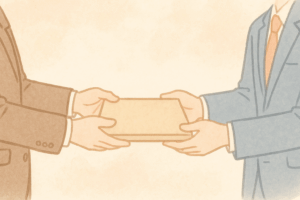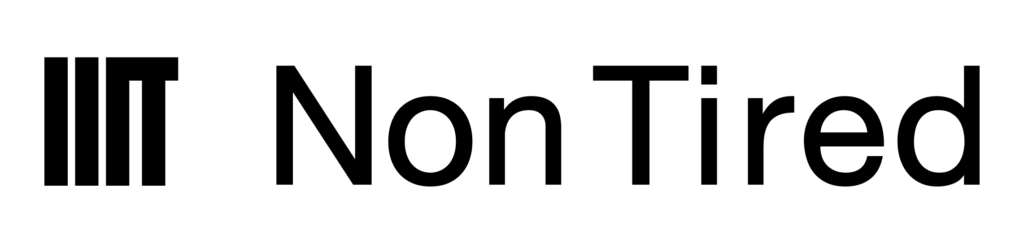定年後に住宅ローンが残ると何が起きる?リスクと生活への影響
定年後は収入が年金中心となるため、住宅ローンの返済負担率が急上昇します。生活費や医療・介護費が増える一方、収入は減少するため、赤字家計に陥りやすくなります。さらに変動金利で借りている場合は、金利上昇リスクにも注意が必要です。
年金生活での返済負担(生活費圧迫、貯蓄取り崩し)
定年後の暮らしを支えるのは、主にこれまで積み上げてきた「資産」と「私的年金」「公的年金」です。
ある調査によると平均額の目安は、会社員・公務員(厚生年金含む)は月額約144,982円、自営業(国民年金のみ)の場合は月額約56,428円とのことです。総務省「家計調査 2023年」よると、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上・妻60歳以上)の実収入は月額約23万円で、消費支出が月額約27万円のため、平均で月約4万円の赤字となります。つまり年金だけでは生活費を賄うことが出来ないため、これまでの資産(貯蓄)を取り崩しながらの生活となります。
また住宅ローンが残っている場合には、以下のように返済負担率が定年後一気に上昇点も注意が必要です。
| 時期 | 手取り収入 | 住宅ローン返済額 | 返済負担率 |
|---|---|---|---|
| 定年前 | 30万円(給与収入) | 9万円 | 30% |
| 定年後 | 22万円(年金収入) | 9万円 | 41% |
医療費・介護費など老後特有の支出増
また加齢に伴い、医療費、介護費用なども増加していきます。年齢別の1人当たり年間医療費(厚労省・医療費の動向より)をみると、40代約17万円、50代約23万円、60代約34万円、70代約57万円、80代以上約93万円と高齢になるほど医療費は急増し、特に 70歳以降は現役世代の3〜4倍にもなります。
実際には、70歳以上の窓口負担は1〜3割(現役並み所得者は3割、それ以外は1〜2割)であり、かつ高額療養費制度(医療費が一定額を超えると自己負担が軽減)があるため、支払い総額は大きくならないような制度設計はされていますが頻度と総額は増加していきます。 介護サービス利用者の自己負担(1〜3割)も在宅介護で月2〜5万円。施設介護で月10〜15万円(特養)〜20万円以上(有料老人ホーム)と介護が始まると支出も当然増えていきます。
金利変動や収入減少リスク
また住宅ローンを変動金利で借りている場合、金利の変動リスクがあります。日本は20年近くデフレ期を推移し、住宅ローンの金利水準についても低い水準で推移していました。2024年3月に日本銀行がマイナス金利政策を解除したことで 金利上昇圧力が強まり、2025年現在では、住宅ローンの固定金利は上昇基調、変動金利はまだ低水準ですが今後上がる可能性は十分にあるでしょう。また定年後も再雇用で働くことも可能です。ただ現役時代と同じ給与というのは難しいため、収入が減少することは想定しておきましょう。更にインフレが加速していくと実質資産が目減りしていきますので、今後の市中金利は注視する必要があります。
定年までに住宅ローンを完済すべき人・完済しなくてもよい人の違い
年金額が少ない、貯蓄が不十分といった人は定年までの完済を検討すべきです。一方で低金利で借りている場合や運用利回りが住宅ローン金利を上回っている場合は、無理に完済しない方が合理的です。判断には老後資金の必要額・資産状況・ローン条件の3点を整理することが重要です。
完済を目指したほうがよいケース
基本的にはFPとしては経済合理性を考えると完済をしない事を推奨していますが、ケースによっては定年退職時までに完済を検討した方がいい場合もあります。例えば年金額が少ない場合は、早めに完済することもありでしょう。特に国民年金だけの場合ですと年金額は平均月額約56,428円のため、ローンの返済負担率が急上昇します。自営業の方は、定年退職という概念がないかもしれませんが、リタイアの時期はいずれ訪れます。早期に完済することでリタイア後の負担を抑えることが可能です。また老後は積み上げてきた資産を取り崩しながらの生活となります。手元の預貯金がどんどん目減りしていくのは心理的にもストレスになるかもしれません。少しでも心理的不安を抑えるという意味で、早期に完済を目指すプランニングをしていくことも選択肢としてもっておきましょう。
完済をせず、毎月返済を続けた方がよいケース
一方で固定金利を低金利で借りている人は、繰り上げ返済(完済)をしなくてもいいかもしれません。0.5~1%程度で借りている場合は、お宝金利かもしれません。また変動金利でも資産を適切に運用をし、住宅ローンの金利より高い利回りを確保できているのであれば、完済をする必要はないでしょう。住宅ローンの返済の基本は「薄く長く」です。薄く長く借りながら運用をしっかりとしていくことで老後の資金の目減りが緩やかになります。とは言え資金が右肩上がりに増加はしないので、少しずつ預貯金が減っていくことを理解し、心理的にストレスを受けずに、コントロールできる人は完済をしなくても大丈夫でしょう。
判断のために必要な3つのチェック項目
完済するか否かを判断する際に必要なチェックポイントが大きく3つあります。
- 老後必要資金の見積もり
1つ目は「老後どういう生活を送りたいか」をイメージし、それが「どのくらいかかるのか」を見積ることです。
毎月の生活費はもちろんのこと、ポジティブな支出:例えば旅行や趣味の費用をイメージして「いつ」「いくらかかるのか」を概算でも見積っておくといいでしょう。またネガティブな支出:リフォームや介護費、老人保健施設の入居費なども同様に見積ることで、老後の生活の資金の流れを把握することが大切です。
- 現在の貯蓄・投資・保険の状況
2つ目は現在の貯蓄、資産運用状況と保険の加入状況について整理しましょう。合わせて今後の収入(公的・私的年金やその他収入など)も加味し、完済しても生活が苦しくならないか検討することが大切です。
一般的には住宅ローンには団体信用生命保険がついています。団信(団体信用生命保険)とは住宅ローン契約者が死亡・高度障害になった場合、残りのローンが保険で完済される制度で、加入条件は住宅ローン残高があることが要件になっています。例えば全額繰り上げ返済(完済)をするとその時点でローンがなくなるので、団信の契約も終了となり、その後は、死亡・高度障害があっても団信での保障はなくなります。完済して団信がなくなった後に必要な保障は、民間保険や貯蓄でカバーする必要あるので合わせて検討する必要があります。
- 住宅ローンの金利・残期間・ローン残高
3つ目は住宅ローンの金利・残期間・ローン残高です。住宅ローン控除が適用されているうちは、完済をするのは得策ではありません。住宅ローンの控除は、年末残高×0.7%(2025年時点)が所得税控除される制度(上限額あり)で仮に控除期間中に完済するとこのメリットが消えてしまいます。
また金利が高い場合は効果的ですが、変動で0.5%程度であれば効果が薄いでしょう。
定年までに完済したい人の返済計画とスケジュール設計のコツ
退職年齢をゴールに設定し、返済期間と毎月返済額を逆算して計画を立てましょう。早期繰り上げ返済は老後の安心感を得られる一方で、預貯金が一気に減るリスクもあります。無理のない範囲でボーナスや不要資産売却も活用し、バランスの取れた返済計画を立てることが大切です。
ゴール(完済年齢)の設定方法
「何歳で完済するか」をまずは設定しましょう。一つの目安としては、退職年齢で判断します。定年退職をゴール設定にする場合はご自身の会社の定年退職年齢が何歳か確認します。会社によっては60歳や65歳と違いがあり、今後もしかすると定年退職が、70歳の会社も出てくるかもしれません。しっかりと情報収集しましょう。
または定年後も再雇用で働く場合は、再雇用終了時期に合わせて完済を考えてもいいかもしれません。
返済期間と毎月返済額の逆算例
定年までに完済するためにはしっかりとした返済計画が重要です。例えば35歳時点で5,000万円を金利1%で借りて返済していく場合、30年ローンを組んだ場合、毎月返済額は約16.1万円になります。毎月この金額を無理なく支払えるのであれば最初から「30年以内」でローンを設定すると定年までには完済可能です。毎月の支払いを抑えたい場合は、20歳で住宅購入をし、35年ローンを組んだり、中には40年ローンを販売している金融機関もありますので検討しましょう。
早期繰上げ返済 vs 繰り上げ返済せず長期返済するメリット・デメリット
早期繰り上げ返済か、繰り上げ返済せず長期返済を続けていくかどちらもメリットデメリットがあります。
早期繰り上げ返済のメリットは
- 老後の生活が安定する(返済額の負担が少ない)
- 心理的に安心する。
老後の生活は、積み上げてきた資産と年金を活用します。高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上・妻60歳以上)の実収入は月額約23万円で、消費支出が月額約27万円のため、平均で月約4万円の赤字となります。これには住宅ローンの返済は含まれていないため、仮に返済額が10万ならば、合計14万円の赤字となります。毎月14万円を取り崩していくと現預金がどんどん減少していくので心理的な負担も大きくなります。退職前までに完済することでこの心理的負担をなくすことができます。
早期繰り上げ返済のデメリットは
- 残高が多く残っている場合、一気に預貯金が減る
- 繰上返済すると団信が無くなる(完済後は生命保険で備える必要あり)
残高が多い場合は一気に預貯金が無くなります。上記メリットと反対になりますが、一気に預貯金が無くなることも負担になります。また繰り上げ返済をすることで、団信も自動的になくなります。
早期繰り上げ返済せず、長期返済するメリットは
- 余剰資金を資産運用に回すことで、更に豊かなセカンドライフを送ることができる。
- 団信が残るので、万が一に備えられる
資金を資産運用に回すことで、取り崩しを緩やかにできます。資産運用はリスクがあるので、理論に基づいて適切に運用することが求められます。また団信が無くならないため、万が一の場合にも対応が可能です。
早期繰り上げ返済せず、長期返済するデメリットは
- 老後収入が減少しても、返済が残るので返済負担率が増加し生活を圧迫する。
- 変動金利で借りている場合、住宅ローンの金利上昇リスクがある。
毎月のローンの支払いが継続するので、返済負担率が上昇します。更に金利の見直しにより、更に返済額が上がる可能性をもあるので、注意が必要です。
双方メリットデメリットがあります。どちらがいい悪いではなく、ご自身に合ったほうを選択しましょう。
固定費削減やボーナス返済、不要資産売却の活用
早期完済をする場合、その資金をどこから捻出するのかですが、手元にある現預金を使用すると資産が減少するので、それ以外をファーストステップとしては検討しましょう。身近な部分ではまず家計支出の見直しと不要品の断捨離を実行しましょう。
毎月の浮いたお金を繰り上げ返済用口座に貯めて、ある程度まとまったタイミングで返済したり、家に使っていない資産価値のあるもの(ワインや時計、ジュエリー等)があれば査定に出して買い取りしてもらうことも有効です。
またボーナスが支給された場合は活用するのもありですが、ボーナスはあくまでも臨時収入です。業績によっては支給されなかったり、金額が変動するので、過度にあてにするのはよくありません。支給されたあとに検討しましょう。
住宅ローン返済と老後資金づくりを両立させる方法(NISA・iDeCo活用)
返済を優先しすぎると老後資金が不足するリスクがあります。NISA・iDeCo・個人年金保険などを組み合わせ、返済と資産形成を並行することが望ましいです。余剰資金をローン返済と投資に分散することで、金利上昇リスクと運用リスクの両方に備えられます。
返済優先しすぎて老後資金が不足するリスク
完済にこだわるあまり、返済を優先し、毎月の生活が苦しくなり、最悪の場合老後資金が不足することは一番避けなければなりません。生活防衛費は目安として、生活費の半年~1年分を必ず確保するようにしましょう。またセカンドライフのライフプランを検討し、ご自身が満足する豊かな生活を送れる範囲での返済を意識しましょう。
NISA・iDeCo・保険活用の組み合わせ方
老後資金の作り方としては、NISA・iDeCo・企業型DCや個人年金保険などを活用します。現役時代に資産運用をしておくことで、金利上昇にも耐えうる家計財務を強固にしておくことで、早期繰り上げ返済も可能になります。例えば若いうちはNISAで資産運用をし、給与が高くなってきたタイミングでiDeCoを活用することで所得控除を生かす方法があります。また個人年金も選択としてはありでしょう。保険は年齢が若いほど保険料が低く設定されるため、同じ年金額を受け取る契約でも月々の負担が軽くなります。また運用成績はNISA・iDeCoで投資信託を活用したポートフォリオ運用のほうがいいかもしれません。ですが、個人年金保険は投資と違って「確定した年金額」が約束される(契約内容による)ため、将来の年金不安に備えやすい点もメリットです。更には所得控除(個人年金保険料控除)が毎年使えるため、若いうちから始めると節税効果も積み上がっていきます。
一方でNISA・iDeCoも同じですが、それぞれデメリットもありますので、どの組み合わせをどの配分でいつから何をやるのかはよく比較検討しましょう。
「完済」と「資産形成」の同時進行プラン
住宅ローンの早期完済と資産形成を同時に進めることは、多くの人が直面する重要な財務戦略の選択です。両方を効率的に進めるためのプランとしては、基本的な考え方として住宅ローンの金利と投資リターンの比較が重要な判断基準となります。現在の住宅ローン金利が1-2%程度であれば、それより高いリターンが期待できる投資に資金を回すことも合理的な選択です。プランのスタートは支出を見直し、住宅ローン返済と投資に回せる余剰資金を最大化することです。ない袖は振れないため固定費の削減や無駄な支出の排除により、月々の投資可能額を増やすことができます。また同時進行を実現するには全額をローン返済に充てるのではなく、例えば余剰資金の50%を繰上げ返済、50%を投資に振り分けるような分散戦略を取ります。これにより、金利上昇リスクと投資リスクの両方に対応できます。
ライフステージ別の住宅ローン戦略(子育て期・40代50代・定年前後)
子育て世代は教育費を優先し、無理な繰上げ返済は避けるのが合理的です。40〜50代は収入のピーク期を活かして繰上げ返済や老後資金の積立を検討。定年前後では退職金の使い方がカギとなり、老後資金とバランスを取りながら返済を進める判断が必要です。
子育て世代(教育費との両立)
子育て世代は、まずは住宅ローンの早期完済を目指す前に、こどもの教育資金を厚くすることが重要です。
教育資金の目安一覧を参考に、家庭の教育方針と照らし合わせて、最低限この金額は確保しましょう。住宅ローン返済をするために学資ローンを借りるのは本末転倒で、一般的には学資ローンを組むより、「住宅ローンの繰り上げ返済を控えて資金を教育費に回す」方が合理的なケースが多いです。
| 進学段階 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年間) | 約70万円 | 約150万円 |
| 小学校(6年間) | 約200万円 | 約960万円 |
| 中学校(3年間) | 約150万円 | 約420万円 |
| 高校(3年間) | 約140万円 | 約300万円 |
| 大学(4年間:文系平均) | 約250万円 | 約540万円 |
| 合計 | 約810万円 | 約2,370万円 |
(※文部科学省「子供の学習費調査」、日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」などを参考)
40代〜50代(収入ピーク期の繰上げ返済活用)
40代~50代は収入のピーク期に入るものの、教育資金も同時にかかるケースも多く、更にはセカンドライフを見据えて老後資金のプールも視野に入ってくるタイミングです。しっかりとライフプランニング、資産運用が若いうちから戦略的に出来ているケースであれば、繰り上げ返済も可能でしょう。
例えば20代~40代は毎月5万円をNISAで資産運用をすると、20年後には2,055万円になっています。これを教育資金として活用。40代~は老後資金として月5万円を定年退職年齢60歳まで運用すると、同じ2,055万円になり、セカンドライフの資金として活用できます。この場合は、60歳時点で退職金が入り、退職金を活用して繰り上げ返済しても老後の生活に影響を与えることは少ないでしょう。ただし変化の激しいこのご時世で、トータル40年間毎月5万円の積立が出来れば…の話ですが。
定年前後(リスク管理と支出最適化)
実務をしていて一番多くご相談を頂くのがこの定年前後の世代からの繰り上げ返済についてです。退職金としてまとまった資金が一気に入ってくるため、長年返済をしてきた住宅ローンから一日でも早く解放されたい!という心理が働き、繰り上げ返済(完済)を検討する方が多いのではないでしょうか。ただここで安直に決断をしてはいけません。まずは今後のセカンドライフをどう生きたいか、そのためにはいくらお金がかかるのか、手元や資産運用の状況をみて、耐えうるのかを複合的に検討したのちに判断しましょう。
FP相談で解決できた住宅ローン完済のモデルケース
退職金を全額繰上げ返済するか、運用しながら返済を続けるかで老後資産の寿命は大きく変わります。実際の相談事例では、キャッシュフロー分析を行い、返済額・年金額・運用益を踏まえて最適な判断を導き出しました。FPに相談することで、具体的な数値に基づいた解決策が得られます。
モデルケース例
50代男性。子どもは既に2人独立し、配偶者と二人暮らし。60歳で定年退職を迎え、再雇用はしない方向
資産残高は1,000万円(預貯金・有価証券・解約返戻金)で退職金は約1,500万円。年金見込額は年間180万円(月15万円)で毎月生活費:30万円(年間360万円)と仮定。退職金は1,500万円でこの時点での住宅ローン残高は約1,300万円(金利1%・残り5年)
相談前の課題
毎月の支出を軽くしたい思いが強く、今後の金利上昇リスクへの不安もあり。一方で公的年金だけで生活費を賄えるか不安があり、資産寿命が尽きないか心配されている。
FPからのご提案
まずは家計のバランスシート(財務状況)を作成し、今後のライフプランとキャッシュフロー(公的年金の受給額)を年金定期便から試算。老後の生活費を年間360万円と仮定した場合、退職金を繰り上げ返済し、残った200万円と預貯金1,000万円を運用しても9年目で資産が尽きてしまう。(以下参照)
| 年 | 年初資産 | 運用益5% | 年間取り崩し180万 | 年末資産 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,200万 | 60万 | 180万 | 1,080万 |
| 2 | 1,080万 | 54万 | 180万 | 954万 |
| 3 | 954万 | 47.7万 | 180万 | 821.7万 |
| 4 | 821.7万 | 41.1万 | 180万 | 682.8万 |
| 5 | 682.8万 | 34.1万 | 180万 | 536.9万 |
| 6 | 536.9万 | 26.8万 | 180万 | 382.7万 |
| 7 | 382.7万 | 19.1万 | 180万 | 221.8万 |
| 8 | 221.8万 | 11.1万 | 180万 | 52.9万 |
| 9 | 52.9万 | 2.6万 | 180万 | −124.5万 |
逆に退職金で繰上げ返済せず運用する場合、手元資金の預貯金1,000万円と合わせて2,500万円を運用する場合、住宅ローン返済は毎月22万円(年間約265万円)になるので年間不足額は(生活費360万円+ローン265万円)-年金180万 のトータル445万円の取り崩しになります。2,500万円を年利5%運用し、年間445万円を取り崩す場合単純計算すると、30年後には資産は約1,200万円程度残る計算となります。
まとめ|住宅ローン完済の最適解は人それぞれ。迷ったらFPに相談を
住宅ローンの完済戦略は、収入状況・金利水準・ライフプランによって大きく異なります。感情的な判断ではなく、客観的な視点で最適解を探すことが重要です。迷った場合は第三者のFPに相談し、老後資金と返済のバランスを最適化することをおすすめします。
自分にとっての最適解は人それぞれ
住宅ローンの早期完済は、金利水準、収入の安定性、家族構成、リスク許容度、他の投資機会など、その人の状況によって答えが大きく変わります。低金利時代なら繰上返済よりも投資に回す方が有利な場合もありますし、金利上昇局面であれば、繰り上げ返済もありでしょう。また安定収入がある人とそうでない人では最適戦略が異なりますし、教育費などの将来の大きな支出予定も判断に影響します。
判断に迷う場合は第三者(FP)の視点を活用する価値
住宅ローンの返済について、戦略的に考えるためには、FPに相談することが重要です。一時の感情での判断ではなく、客観的な立場から顧客本位のアドバイスが可能です。、また税制優遇や制度の活用方法を熟知している点も大きな支えになります。また住宅ローンの返済が起点だとしても、団信の変更に伴う保険の見直しなどライフプランニング全体を俯瞰して助言できるのも強みでしょう。
行動を始めるタイミングと準備の重要性
またこれは見落とされがちですが、早期完済を決断した時の市況、金利環境、個人の状況などによって効果が変わりますし、実行前の資金計画や緊急時資金の確保なども重要になってきます。
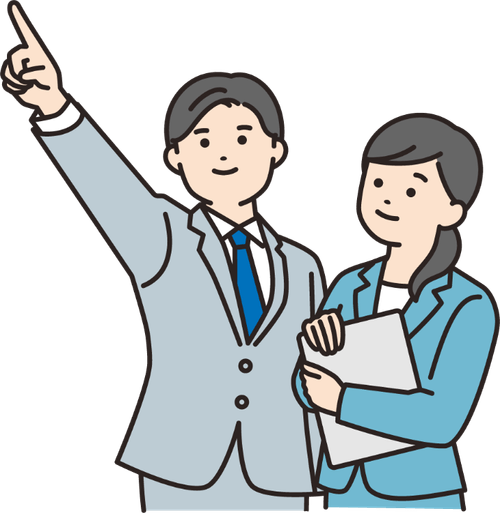
売らないFP コーパス
あなたに寄り添ってお悩みを解決できる
信頼できる独立系FPだけを紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えられるFPとマッチング!
もうFP選びで失敗したくない方へ
売らないFPコーパス
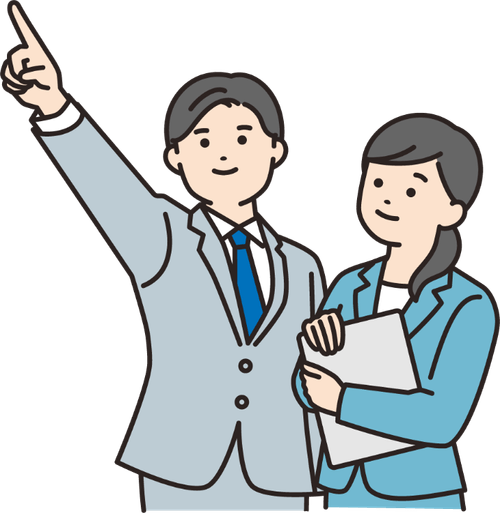
あなたに寄り添って解決できる
信頼できる独立系FPだけを
紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えるFPと
マッチング!
監修者情報:芳川 宏輔

株式会社ウィンカム
CFP認定ファイナンシャルプランナー
金融商品・保険商品を一切販売せずコンサルティングに徹するFP。
保険・住宅ローン・資産運用・NISA等サポートは多岐に渡る。
年間100回以上の面談を実施し、延べ相談実績は300回を超える。
- 当該資料は信頼できる情報、データをもとにNonTired株式会社が作成しておりますが、正確性・完全性に関して当社が保証するものではありません。
- 当該資料に記載された情報、意見は作成時点のものであり、その後の情勢の変化などによって予告なく変更することがあります。
- いずれの情報、データ、意見は将来の傾向などを保証もしくは示唆するものではありません。
- この資料は、投資行動や意思決定を推奨するものではなく、利用者はご自身の責任において活用してください。
- 当該資料に係る一切の権利は引用部分を除いて弊社に所属し、いかなる目的であれ当該資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りします。