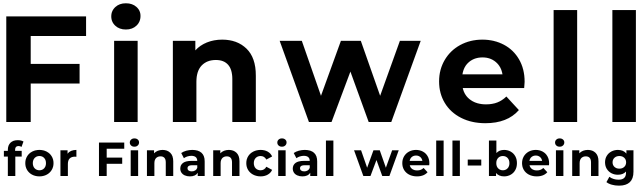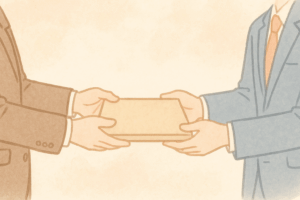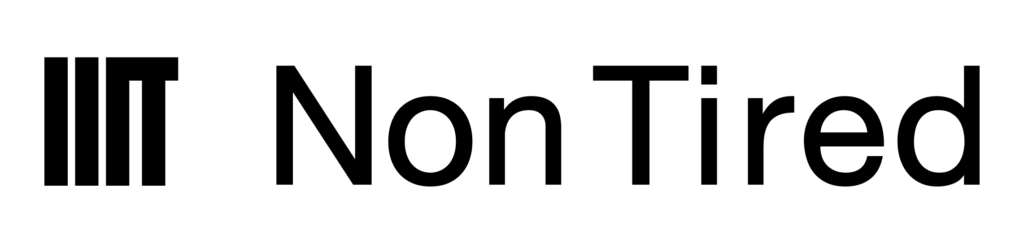専門家が行う資産運用の実態

ここでは独立系FPの芳川さんが実際に行っている投資について触れていきます。
話題の新NISAやiDeCoについてのお考えもインタビューしました。
コーパス編集部:
芳川さんが実際にどのような資産運用や投資を行っているのか、専門家の視点からお話しいただけますか?

私もNISAをフル活用しています。
年360万円の上限を有効に使い、基本は積立投資を中心に行っています。
投資先としては、株式と債券のインデックスファンドを組み合わせています。
割合は株式70%、債券30%くらいです。
かなり堅実な運用で、派手さはないですが、長期的には安定した運用が期待できると思います。
コーパス編集部:
一括投資と積立投資の違いについて、どうお考えですか?

経済合理性の観点からは一括投資が最も効率が良いというデータもあります。
ただ、人間の感情が絡むので、タイミングによっては「もっと待てばよかった」という後悔が生じやすいです。
そういった不安を避けたい方は、積立投資の方が安心感があるでしょうね。
お金の勉強の必要性とFPの役割
コーパス編集部:
最近、金融教育の必要性が叫ばれていますが、一般の人もお金の勉強をするべきだと思いますか?

絶対に学んでほしいですね。
投資や金融商品については、最低限の知識があれば、専門家に頼った際にも自分で判断ができるようになります。
FP3級レベルの知識は、国民全員が持っていても良いと思います。
コーパス編集部:
専門家に丸投げするのではなく、自分でも理解しておくことが大事ということですね?

そうです。丸投げしてしまうと、悪徳な専門家に騙されるリスクもあります。
自分の金融リテラシーを高め、専門家のアドバイスが正しいかどうか判断できるようになることが重要です。
資産運用と投資の心構え
コーパス編集部:
資産運用でリスクをとるかどうかの判断は、どのように行うべきでしょうか?

資産運用はリスクとリターンのバランスが大事です。
たとえば、年齢や収入によってリスク許容度は変わります。
若い方であればリスクを取っても良いですが、リタイアに近い方は、より保守的な運用を考えるべきです。
大事なのは「なぜ運用をするのか」という目的を明確にすることです。
投資のポートフォリオとバランスの重要性
コーパス編集部:
最近は「これだけ投資しておけば間違いない」という情報も見受けられますが、偏った投資はリスクが大きいですよね?

はい。投資の基本はポートフォリオのバランスです。
NISAで投資信託を運用している人でも、他の資産を含めて全体のバランスが偏っているケースがあります。
例えば、実家の不動産や親から受け継いだ株式など、全てを考慮した上でバランスをとることが重要です。
投資の制度とふるさと納税の位置づけ
コーパス編集部:
NISAやiDeCo、ふるさと納税など、一般の方が活用できる投資制度についての考えをお聞かせください。

NISAはまず最初に活用すべき制度です。
非課税で運用できるため、非常に有利です。
iDeCoも老後資金を確保するのに最適ですが、60歳まで引き出せないというデメリットもありますので、注意が必要です。
ふるさと納税は節税というよりも、2000円の負担でお得な返礼品をもらう制度と考えた方が良いでしょう。
政治や制度変更がFP業務に与える影響
コーパス編集部:
総裁選や東京都知事選など、政治の動きが大きくなる局面で、FPの視点からどういう影響が考えられますか?

政治的な動きや制度の変更は、FPの業務にも影響を与えます。
例えば、年収の壁の撤廃が進めば、共働き世帯の収入が増え、家計全体のライフプランに大きな影響を与える可能性があります。
FPとしては、そういった制度の変化を常に注視し、お客様に最適な提案をできるように準備しておく必要がありますね。



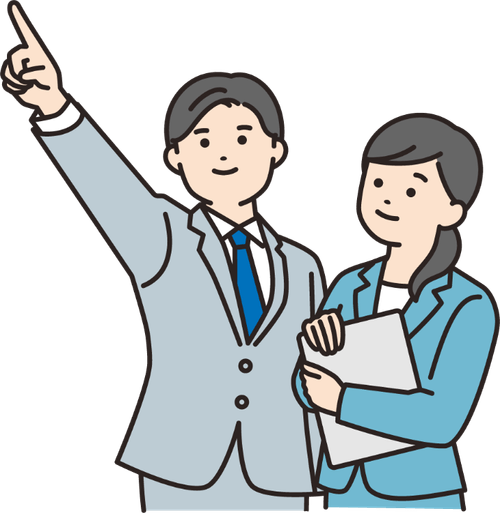
売らないFP コーパス
あなたに寄り添ってお悩みを解決できる
信頼できる独立系FPだけを紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えられるFPとマッチング!
もうFP選びで失敗したくない方へ
売らないFPコーパス
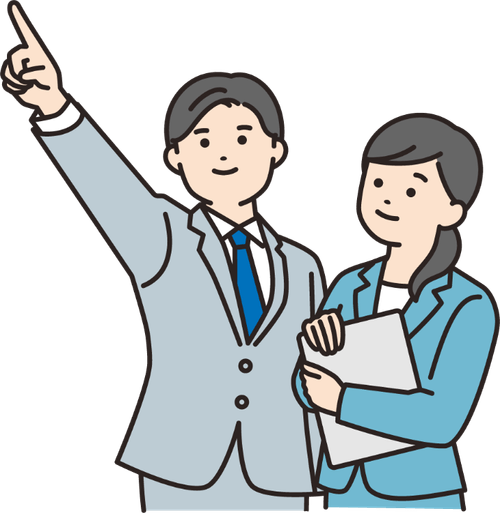
あなたに寄り添って解決できる
信頼できる独立系FPだけを
紹介するサービスです
特定の商品を売ることを目的とせず、
あなたのお金の相談に真摯に応えるFPと
マッチング!
監修者情報:芳川 宏輔

株式会社ウィンカム
CFP認定ファイナンシャルプランナー
金融商品・保険商品を一切販売せずコンサルティングに徹するFP。
保険・住宅ローン・資産運用・NISA等サポートは多岐に渡る。
年間100回以上の面談を実施し、延べ相談実績は300回を超える。
- 当該資料は信頼できる情報、データをもとにNonTired株式会社が作成しておりますが、正確性・完全性に関して当社が保証するものではありません。
- 当該資料に記載された情報、意見は作成時点のものであり、その後の情勢の変化などによって予告なく変更することがあります。
- いずれの情報、データ、意見は将来の傾向などを保証もしくは示唆するものではありません。
- この資料は、投資行動や意思決定を推奨するものではなく、利用者はご自身の責任において活用してください。
- 当該資料に係る一切の権利は引用部分を除いて弊社に所属し、いかなる目的であれ当該資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りします。